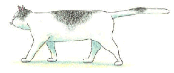
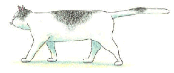
|
[2003/07/01] 詩のマルシェ(市) 約1年振りでパリの地を踏んだ。蒸し暑くなりはじめた東京を離れてカラっとした気候のもとでリフレッシュできるかと思いきや、連日の猛暑に少しバテ気味になってしまった。毎日晴れて青い空が広がる。『ぶらぶら猫のパリ散歩』にも書いたとおり、パリの空は本当に青く、そして広い。ビルが密集するパリの空が広いだって?と訝(いぶか)る人もおいでかもしれないが、今回改めてつくづくとそう感じたのだ。ビルの高さはせいぜい7階建て(約20m)で同じ高さの建物が並ぶためスカイラインがすっきりとしているし、視界にいやらしくとびこんでくる電線がないために、ただでも青い空がスコーンと突き抜けるように気持ちよくパリの上に広がっている。 当日会場となっている6区のサン・ジェルマン・デ・プレ地区にある新古典主義様式のサン・シュルピス教会前の広場に行ってみると、予想通り、ブックフェアの詩に特化した小型版だった。各出版社の小さなブースが並び、各ブースには本が並べられて、大勢とまではいかないが、それなりの賑わいを見せている。詩の市がたつだなんて、さすがは文化大国、ボードレールやランボーの国フランスと感心。 友人が手伝うと言っていたのは唯一の日本の参加出版社である詩学社のブース。現在ある詩の雑誌としては一番古いと編集長の寺西さんが自負する雑誌『詩学』を発行する日本の詩出版の老舗であるこの小出版社が、噴水に近い広場中央部分で、あのフランスの大出版社フラマリオンの正面を堂々と占めている姿は頼もしい。ここで寺西さんがフランス・メディアのインタビューを受けるその手伝いを彼はするというのだ。詩人からは遠く離れてしまったとはいえ、詩に対する思いを捨てきったわけではないぶらぶら猫は、結局、6月21、22日の2日間にわたってこの詩学社さんのブースをうろつき、昨今の詩をめぐる興味深い話を盗み聞きすることができたのだった。 結論を先に急ぐとぶらぶら猫は二重のショックを受けた。ひとつはこのような日本では考えられな もうひとつは、しかしながら実はフランスにおいても詩をとりまく環境は非常に厳しいものがあるということ。詩の市会場で購入した詩の専門紙『オージャードウィ・ポエム(詩の今日)』によると、次のようにある。「フランスにおいて、詩は一般大衆のみならず知識階層やメディアの間でも軽んじられている。詩の雑誌はたくさん発行されているし、詩に関する催しも活発におこなわれているようにみえるが、実は詩集をだしても500部足らずしか売れず、雑誌の購読者も200人に満たず、補助がなければやっていけない状況なのだ(要約:藤野)」 確かにこの数字では商業的になりたつのは難しい。学校などでも古今の名作を徹底的に暗記させられ、およそ文学に興味のないように思える一般の高校生までもが母国の偉大なる大家の作品の一説をそらんじると言われるほどにフランス人=詩が好きというイメージを勝手にいだいていたが、そうしたレッテルがはがれ落ちてゆくとともに、どこでも芸術が生き延びるのは難しいのだという現実をつきつけられた。せめてフランスは日本とは違ってあってくれという甘い幻想が崩れ落ちたのだ。 しかしよく胸に手をあてて考えてみれば、そう言うぶらぶら猫も偉そうなことは言えない。フランスも日本もおよそ現代の詩人をほとんど知らないし、ここ数年詩集など買ったこともない。マルシェ・ド・ラ・ポエジーの会場をうろついていてもヴェルレーヌやマラルメの名前には目がとまるが、 市の終了前に、かつてパリを走っていたというレトロなバスに藤富保男氏をはじめとする日本から来た詩人たちと観客をのせてパリ市内を走りながら行うという詩のパフォーマンスに参加した。同乗していたフランス人たちの観客がどれだけ理解していたかは疑わしいが、それなりの盛り上がりにまずはめでたし。短歌や俳句を生んだ「詩大国」日本の詩のこころがどれだけパリジャン、パリジェンヌのクール(こころ)に響いただろうか?
*筆者 藤野優哉(ふじの・ゆうや):元編集者。1999年より1年間、絵描きを目ざしてパリに留学。3月に新宿書房より『ぶらぶら猫のパリ散歩──都市としてのパリの魅力研究』刊行。2003年6月17日~7月17日にかけて再びパリに滞在。 |