前回のコラム(70)に対して、鉄道写真界のレジェンド大木茂さん(『汽罐車(きかんしゃ)―よみがえる鉄路の記憶1963-72』 新宿書房、2011の著者)から、すぐさま反応があった。わがコラムはこう書いてしまった。「1938年(昭和13)4月17日午前10時50分、28名の農民たちが清里駅に下車した。小海線は1933年に全線開通していた。・・・」
大木さん曰く、「小淵沢から清里まで鉄道が開通したのは1933年ですが、清里~野辺山~信濃川上間が開通し、全線で運転が始まったのは1935年11月です」。
清里までの開通年と小海線の全線開通年を取り違えてしまったのだ。ただちに、コラムを「小海線は1935年に全線開通していた」と訂正した。そして大木さんは、自分のウェブサイトの「小海線」に招待してくれた。写真集『汽罐車』に収録できなかった小海線の写真もある。ぜひお楽しみください。大木鉄路劇場はいつも迫力満点だ。撮影時期は1970~72年で、ディーゼル化のため72年10月1日には小海線から蒸気機関車が消えた。あの清里ブームはまだまだ来ていない。
大木さんのコメントは続く。
「さて、最後のクイズ。1938年の奥多摩の農民たちは、どうやって清里まで来たか?
1 大菩薩峠の脇、柳沢峠を越えて塩山に出た。
2 松姫峠を越えて大月に出た。
3 青梅まで歩き、立川に出た。
小河内、小菅あたりの標高は500~600mです。柳沢峠は1500m、松姫峠は1200mほどあり、1,2はないでしょう。その代わり、小菅から 900mの鶴峠を越えて上野原に出た可能性はあるかと思います。しかし、小河内から多摩川沿いにほぼ下り道を歩き青梅に出た、と考えるのが妥当でしょう。
50年近く前、徒歩ではありませんが車で、柳沢峠、松姫峠、鶴峠を走り回ったことがありました。今ではどこも舗装された幅広い道路になっていますが(松姫峠などは長いトンネルで抜けています)当時は細い砂利道、恐ろしいような道でした。90年前はどうだったのだろう?」
わたしも3つ目の青梅~立川コースだと思う。東京府の小河内村の村民は当然、ふだんから青梅に向かうだろうが、多摩川の源流にある山梨県の丹波山村や小菅村の村民も、当時も今も精神的には東京が近く、小河内から青梅に向かったに違いない。丹波山村には現在も丹波(たば)~青梅駅間に西東京バスが一番のアクセスとして走っていて、山梨と直接結んでいる公共交通機関はない。
★
小河内ダムの立案から起工まで7年も時間がかかった。補償交渉は長引く。水没予定地の各村人たちは、畑の耕作をひかえ、移転の日を待つ。交渉が長引いた理由は、東京市と川崎市との水利問題が大きかった。また、このあたり多摩地方は、江戸末期から明治にかけて行政的にも大きな変動があった。
小河内村は1889年(明治22)の町村制により、神奈川県西多摩郡小河内村になる。多摩の中心地、八王子も神奈川県南多摩郡八王子町となった。北多摩郡も神奈川県。あの吉祥寺も神奈川県だった。1859年(安政6)の横浜開港以降、日本の生糸はこの横浜から西洋に大量に輸出されるようなった。かつては「桑都(そうと)」と呼ばれた八王子は多摩の近隣地域だけでなく、埼玉や群馬などの関東周辺や長野からも生糸が集まる町となった。生糸や絹製品は馬、人力により、八王子から南下し、原町田をへて横浜港に向かった。八王子と横浜を結ぶこの「浜街道」は、後年「絹の道」とも呼ばれた。絹の道を生糸商人や西洋人が行き来したのだ。
多摩地方の往来先、人々の目は西の東京には向かず、南の横浜に向いていた。この絹の道からさまざまな西洋文化が多摩の山奥の五日市の豪農の手元に届けられた。その後この地域は自由民権運動が盛んになる。ところが、1893年(明治26)に、神奈川県に属する三多摩全体が東京府に移管された。小河内村は東京府西多摩郡になり、八王子町は東京府南多摩郡となる。その間、甲武鉄道開通(新宿~八王子:1889年)、青梅鉄道開通(立川~青梅:1894年)と、交通手段も街道から鉄道にかわり、人々の往来も横浜から東京へと変わっていった。
小河内ダムが川崎市と東京間での水利問題で着工がなかなか進まなかったのは、このような強引な三多摩全域の東京府移管への、神奈川県民の恨みもあったにちがいない。
小河内ダムは戦争のため工事を中断していたが、これが再開したのは1948年(昭和23)9月からだ。数年後この小河内村に新しい住民(お客)が登場した。それは「山村工作隊」だ。日本共産党は1951年2月に反米武装闘争の方針に転換した。山村工作隊が組織され、全国各地の農村・山村に派遣された。特に小河内ダムが多摩川の下流にある在日米軍の立川基地や横田基地の電源になる「軍事ダム」だということで、多く学生(後に映画監督となる土本典昭もいた)や前衛美術家(山下菊二、桂川寛、勅使河原宏ら)*たちがダム建設反対を訴えに小河内村に入った。しかし、かれらは村では相手にされず、日本共産党も1955年に「農村から都市を包囲する」という武装闘争方針を放棄し、山村工作隊の活動そのものも誤りであったとされた。
幕末から明治そして昭和にわたる多摩の歴史、これを「記憶する土地(地形)」を見事に辿った本がある。原武史さんの『地形の思想史』(角川書店、2019年)だ。角川の月刊PR雑誌『本の旅人』に連載され、同誌が2019年9月に休刊した後、連載は『野性時代』に引き継がれ完結、単行本化された。
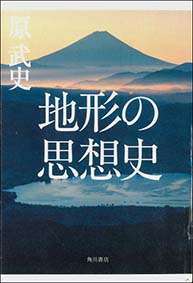
カバー:表紙
岬、峠、島、麓、湾、台、半島という7つの景色の中にある独特な地形、伝説。そこに滞在し、あるいは生活する人々との極めて強い関係が見られる数々の地形を、実際に歩いてみたルポである。
この中で、第2景の「峠と革命」が圧倒的に面白い。わが敬愛する鉄ちゃん歴史家・原武史さんだが、今回はいっさい鉄道を使わず、車で道を行く。スタートは「浜街道」(絹の道)の起点の八王子。そこから、秋川街道―小峰峠(294m)―五日市(武蔵五日市)―檜原村・檜原街道―本宿(もとしゅく)―数馬(かずま)―風張峠(かざはりとうげ1163m)―月見野―奥多摩湖(小河内ダム)―青梅街道―岩崎貞夫の記念碑―(山梨県)丹波山(たばやま)村・鴨沢―丹波―大菩薩ライン―柳沢峠(ここで多摩川水系から笛吹川水系へ)―大菩薩峠入り口・福ちゃん山荘までのコースだ。
五日市では「五日市憲法」の草案が発見された深沢家屋敷跡へ。五日市憲法は絹の道が横浜から運んできた新しい市民思想からうまれた。風張峠を越える。ここは急峻な峠、五日市と小河内との間の行き来は、なかなかたいへんだったろう。眼下に奥多摩湖。湖底にはダムに沈んだ小河内村の集落があった。小河内ダムによって、最終的に945戸6000人が山梨の清里、青梅、昭島、福生、八王子などに移住させられた。この小河内ダムが完成したのは1957年11月。寺の境内にある岩崎貞夫の記念碑に向かう。山村工作隊員の岩崎貞夫は2度にわたる逮捕後も小河内にもどり、山村工作の活動を続けるが、1953年10月に35歳で病死する。党からも切り捨てられ、歴史からも忘れ去れた山村工作隊、そのひとりの隊員のためにかつて「同志」が建てた唯一の記念碑だ。「五日市憲法」が陽の歴史とすれば、山村工作隊は陰の歴史だ。そして、鴨沢。ここは清里開拓民の故郷のひとつだ。最後の福ちゃん荘は1969年11月に共産主義者同盟赤軍派のメンバーがここに宿泊し、付近の山中で武装訓練をしていたところを、凶器準備集合罪で53人が逮捕された。
先週の3冊と原さんの本から、気になっていた清里開拓民の歴史の一端を知り、丹波山、小菅、小河内各村の社会史をもう一度考えることになった。多摩川の源流沿いにどこまでも続く集落。そこで生きる人々は、まるで回廊のような地形の中で、時代に翻弄されてきた。しかし土地はそれを記憶し続け、さらに新たな歴史を産み出していくのだ。
*参考サイト
1)
https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK21022.....
「吉祥寺・町田は昔、神奈川県だった 知事が捨てた街」
「多摩の東京移管問題の背後に政治的思惑?」など
2)
https://artscape.jp/artword/index.php/『週刊小河内』
桂川寛さん(1924~2011)は装丁家・桂川潤さんの父親である。本コラム(15)を参照。

