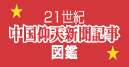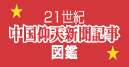 (2) [2003/07/13]
鷹木敦
(2) [2003/07/13]
鷹木敦
『不食病』/『三年食べない女』
『食わず女房』という昔話がある。欲深い男が、「飯を食わずによく働く嫁が欲しい」などと身勝手な事を言っていると、ある日本当に「私は食べません」という女性が現れる。結婚してみると、まさしく言葉の通り、何も食べずによく働く。燃費ゼロで、お隣の牝牛の「花子」よりよく働く。時々、自分でもよくわからなくなるのか、笑顔で「モー」などと鳴いたりしている。女の鑑である。
ところがほどなくして男は、奇妙な事に気が付く。櫃の米の減りが尋常でない。不審を抱いた男が、「ちょっと町まで」と出かける振りして舞い戻り、天井裏から家の様子を窺ってみると、女房が下で特大の握り飯をこしらえている。「ははあ、他に男でもいたのか」などと一人首肯していると、不意に女房が深々とうつむき、首をぐいっと捻った。長い黒髪が頭頂部からばっさり掻き分けられ、ひくひくと蠢く化け物のような口が現れた。髪に隠されていた醜怪な口が、握り飯を次から次へと飲み込んでいく。米が減っていたのは、このせいだ。女房の頭には、知らない口があった。腰を抜かした男は、足を滑らせ音をたててしまう。「きっ」。天井を見上げた女房と目が合った。人の目ではなかった。もはや鬼婆だった。「...見たなあ!」四つん這いになった鬼婆は、両手両足の爪突き立て、ヤモリの如くぐいっぐいっと身捻り壁を攀じ登り、男の隠れる天井間近へあれよあれよと迫り来る...。

- 「だいたい、こんな感じ」
- (「二口女」/『桃山人夜話』、天保12年)
日本各地に広範に分布する説話で、女房は「鬼婆」や「山姥」、或いは蛇や蜘蛛の化け物だったりする。大概この後、自分で作らせた桶の中に男を押し込めると、そのまま背負って山奥深く連れ去って行く。
「女は見ていないところで、実は結構食べている」「一人でいる時の女性の生態は実は結構ショッキングなので、男は決してこれを見てはならない」という、たいへん深い洞察に基づいた、含蓄溢れる、実にためになる昔話なのである。
ところがこれに関し、先日の中国の地方新聞にまことに驚くべき記事が掲載されていた。現在、中国にはこの「食わず女房」が実在するというのだ。大連市在住の女性で、三年もの長きに渡り、食事を一切口にしていない。時々水を飲むだけだ。にもかかわらず、自ら経営する理髪店で連日休まず、精力的に働いている。記事を読む限り、鬼婆でも蜘蛛の化け物でもないらしい。中国共産党との関係も深い、「遼寧晩報」からどうぞ。
|
唯一の食事:「水一杯」
唯一の願い:「『怪人』と呼ばないで」
『三年間、米粒ひとつ食べない女』
奇怪だ!三年間一口も食べずに、普通の生活!これは大連在住のある女性の身に、実際に起きた出来事だ。
記者は昨日、公安部の協力を得てこの女性を取材する事ができた。理髪店経営の女性、冷雲さんは今年52歳。3年前のある日、多忙により朝食・昼食共に取り損ねた彼女は、午後三時にいつもの揚げパンを買ってきた。ところが食べ終わるなり気分を悪くして全てもどし、その後二日間何も口にしなかった。自分でも奇妙に感じたのは、その間空腹感を全く覚えなかった事。
自ら病気を疑い、地元病院で検査を受けたが全て正常。更に大連市の大病院を幾つかまわり検査したが、やはり異常なし。摂食障害の可能性を考えた医師もいたが、こうした患者に見られる体への悪影響が、彼女には全く見られず、全機能正常。結局原因はわからず、冷雲さんは病院通いをやめてしまった。
こうして彼女は、2000年5月から食事を取っておらず、毎日夕方に飲む一杯の水が、唯一の「食べ物」なのだという。当初は小便があったが、不思議な事にここ30ヶ月間は、大小便が一切ない。長いこと悩まされていた頭痛、リューマチ、胃病等も、不食になってから奇跡的に全てが好転した。頻繁に風邪を引いていたのが、今では病気知らずの精力旺盛。現在、理髪店で連日10時間以上働いているが、全くの疲れ知らずだ。
唯一の良くない変化は、たいへん痩せてしまったこと。元々62キロあった体重が、2000年末には45キロにまで減少。しかし、それから2年以上、更なる減少はない。
彼女の理髪店はたいへん繁盛しており、取材中も忙しく立ち回っていた。彼女は記者に対し親切だったが、取材を望んでいない事もはっきりと告げた。自分の「奇病」が報道されて、人から「怪人」視され、生活を乱されたくないからだ。「奇病」により有名になるのは、なお望まない。取材が、「彼女の病気をなんとかしてあげたいという好意から」である事を記者が何度も説明し、ようやく取材を了承してくれた。彼女は、自分は普通の生活を送っているがやはり病人なのであって、自分の病気が一体何なのか知りたい、と記者に告げた。また、自分の事を「怪人」と書かないよう、何度も記者に頼んだ。
(遼寧晩報2003年6月9日)
(以上、要約。中国語原文記事はこちらから)
http://lswb.lnd.com.cn/show.php?id=7210&class=??新?(遼寧晩報「大連奇女子三年不食一粒米」)
|
「怪人と呼ばないで」「怪人と書かないで」と何度も嘆願され、共感たっぷりに深々うなずいておきながら、身をねじって原稿に向かうなり、迷わず「奇怪だ!」などと書き始めてしまうあたり、いかにも中国の新聞で困ったものなのだが、まあそんな記事。
更にはこの記事、本人の住所・氏名に、あろうことか女性の排便周期までデカデカと掲載している。どこが「好意の記事」なのだか、なんだかよくわからない。
翌日の記事で、記者は中国各地の「名医」への取材を敢行。「確かに、摂食障害ではないようだ」「信じられない」「そのような症例は聞いた試しがない」などといった、何の役にも立たないコメントの数々を一つ一つ丁寧に紹介している。
さて、実は日本では江戸時代に既にこの病気が報告されている。18世紀に生きた、ある少女の身に実際に起きた出来事だ。この少女、思春期の頃より次第に小食となり、同村の者と結婚するもうまくいかず、愛知県は長寿寺の尼僧となった。そうする間にも不食は次第に進行、食事が月に二三度から数ヶ月に一度となり、ついに完全な絶食状態へ。時折湯を飲むだけだが、それでも体調には問題なく、数十日間の参詣旅行も一食もせぬまま成し遂げ、終いには「生き菩薩さま」として、人々の信仰の対象となってしまった。百井塘雨が実際にこの尼僧に会見して記録、医師の橘南谿(なんけい)も著書でこれに言及している。
この尼僧の場合「完全な絶食」「水分のみ摂取」「精力的に勤務」といった具合に、現代の冷雲さんの症例と完全に一致しており、二人が同じ病気に罹患していた可能性は高い。
更に遡ると、同じく医師の香川修庵が「不食病」に関する医学的記述を残しているが、どうやらこちらは二人とは異なり、現在でいう摂食障害「神経性無食欲症」(いわゆる「拒食症」)の祖のようだ。症状はともかく、「三十数人の多くは女性で、男性は二、三人のみ」(1) とあるから、これは約90%が女性という、現代の摂食障害の男女発症比率とほぼ一致している。橘南谿も「余も数人を療せしかど、しかと手際よく癒えたることなし。婦人に多くあり」(2)とする。一般に「産業化社会特有の病気」とされているが、男女比に関しては18世紀封建社会から然程変わらないのである。
現代の「拒食症」の女性も、その痩せ細った体からは想像し難い過活動性を見せる事がある。だが彼女らは、「食わず女房」が夫に隠れ、「もう一人の自分」と化して無茶食いをしていたように、「拒食」と「過食」を繰り返すタイプでない限り、通常「痩せ細って」いるのである。飢餓・自殺・電解質異常等で、カレン・カーペンターのように、不幸にして死に至る事もある。ところが、中国の冷雲さんは体重45キロで何年も安定しているし、18世紀愛知県の尼僧に至っては、むしろ「支体肉肥て」(3)いたという。
ストラボンの『地理誌』に、当時ガンジス川源泉一帯に住んでいたという、「口なし人」に関する記述がある。「肉を焼く時に出る湯気と果実や花の香りで身を養い、従って口がなく、代わりに呼吸孔を持っている」のだそうである(4)。いくら紀元前後のインドとはいえ、そんな非常識な事を平気な顔でされては人類学者が困るのであって、せめてビーチで寝そべって光合成ぐらいはしてもらいたいのだが、こうした話は、洋の東西を問わず何千年も前から時折湧いて出ては世を賑わすのである。
橘南谿は、こうした「完全な絶食人」の多くを「然れども、かかる奇怪のことには多くは姦民の人を迷わして金銀をむさぼることにあり、十に八九は信じがたき事なり」と一蹴する。しかし「十に一」はその可能性を認めているのであって、件の尼僧も当時「怪しい事を行って人民を惑わすものではないか」と、お上の取調べを受けたが、結局「ただの病気なので仕方がない」と釈放されている。金銭には興味がなく、「人に知られたくない」と取材も固辞し続けた冷雲さん、報道に接した地元の病院で、再び診察を受ける事になった。さてさて、真相や如何に。

- 「私はお腹に口がありますが、やっぱり元気」
- (中国古代の「形天」さん/『山海経』、挿絵は清代)
- 注
- (1) 香川修庵『一本堂行余医言』18世紀
(2)
橘南谿『東遊記』1795年
(3)
百井塘雨『笈埃随筆』1790年頃
(4)
ストラボン『地理誌』第15巻「インド」1世紀
*鷹木敦(たかぎ・あつし)1971年生まれ。作家・臨床心理士。著書『お笑い超大国中国的真実』(2002年、講談社)
|