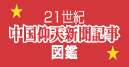 『最後の女人国』 1682年10月末、伊豆から一人の日本人が東南海の彼方目指し、同心の友を引き連れ船出した。 「これより女護(にょご)の島にわたりて、抓(つか)みどりの女を見せん」「譬(たと)へば腎虚してそこの土となるべき事、たまたま一代男に生まれての、それこそ願ひの道なれ」 好色丸(よしいろまる)と名づけられたこの船には、何故かあきれるほど各種各様の性具・強精剤が山と積まれている。潮風を頬に受け、意気揚揚として陣頭指揮取る齢六十のこの男こそ、17世紀日本が世界に誇る不世出のプレイボーイにして、井原西鶴『好色一代男』(1682年)の主人公、「世之介(よのすけ)」その人である。 7歳にして早くも性に目覚め、莫大な親の遺産を相続するなり、連日贅の限りを尽くした豪遊三昧。こんな事を27年も続けていたら、いつの間にやら60歳。いい加減本土での遊郭遊びにも飽きてきた世之介が、好色遍歴の最後の大舞台にと選んだのが、東南海の彼方に浮かぶという「女護(にょご)の島」。 これ即ち、「女だけが住み、たまに男が漂着でもしようものなら、たちまち発情した女たちが群がって来てつかみ取り。あれよあれよと男子の本懐を遂げられ、夢か現かわからぬ間に、精が尽きて天国へ」などという、まさしく夢のような垂涎不止的「女人国」なのである。近世日本では、伊豆七島の八丈島こそ、この伝説の「女護の島」であると信じられていた。世之介が伊豆から出航したのは、理由あっての事である。 この「女人国」、やはり中国からの影響がある。古代の地理書『山海経(せんがいきょう)』に、早くも「女子国」「女子之国」の記述が見える。三蔵法師と猪八戒が、「西梁女人国(せいりょうにょにんこく)」で川の水を飲んで妊娠してしまい、僧侶のくせして「堕ろす、堕ろす」と大騒ぎしたのは、ご存知の方も多いでしょう。世之介が目指した「女護島」の起源を、南宋の『嶺外代答(れいがいだいとう)』(12世紀)の「女人国」に求める研究もある(1)。『嶺外代答(れいがいだいとう)』の説話は、当時インドネシア周辺海域に流布していた現地説話を南海商人経由で取り入れたものだともいうから(2)、ずいぶんインターナショナルな伝説なのである。  (『西遊記』) この「女人国」、東南海の島にあり、住民は南風に遭うとなぜかおおいに発情して、即妊娠。生むのはやっぱり娘ばかりで、たまに男性が漂着するとたちまち捕らえられ、数日で昇天させられてしまうとのこと。これでは天国なのだか地獄なのだか、なんだかよくわからない。ともかく世之介、西鶴の神筆に操られるまま、八丈島辺りにぼんやりと重なり合って描かれた「女護の島」目指し、一直線に出航した。 ところが、この「女人国」に関する驚くべき記事が、つい先日の中国の新聞に載っていた。中国には、今なお「最後の女人国」なるものが存在するというのある。住所までしっかり書いてある。四川省と雲南省の境だ。日本から見ると、南東ではなくて南西。世之介、はなから方角を間違えていた。指につばつけ風向きなど見ているヒマがあったら、きちんと新聞を読んでから出航するべきだった。上海の新聞、『新聞晩報』の記事からどうぞ。
「1500年以上居住する」というのが事実ならば、当然世之介が船に乗った1682年10月末にも、この地に「女人国」が実在していたわけで、返す返すも方向違いが悔やまれる。 残念ながら、私たちがふらふら遊びに行っても「わっと現れた美女軍団がつかみ取りにして喰って」はくれないようだが、奈良時代のような「妻問い婚」(中国語:「走婚(ツォウフン)」)が、21世紀の今なお行われているというのだから、興味深い。男は夜、秘密の合図を持って彼女のもとを訪れ、夜明け前に、見つからぬようこっそり帰っていく。「妻問い婚」「流動的結婚」。まさしく万葉集の世界だ。 実はこの集落、以前から知られていて、文化人類学者達が様々な研究を行ってきた。最近では、中国側が「東方女人国」などと名うって観光資源化も進められているから、行った事がある方もいるかもしれない。もっとも、文化大革命時代には、「婦人連合会」の頭目あたりがしゃしゃり出て来て、物凄い剣幕で一夫一妻制を押し付けていたというから(3)、ご都合主義もいいところなのだけれども。商品経済と異文化の流入で、「妻問い婚」も以前ほど自由ではなくなってきているようだ。 いずれにせよ、過去数千年間にわたり、嫁は夫の家の所有物、男の子を産んで初めて存在を認められ、更には一妻多妾、幼児婚に売買婚は当たり前、はたまた妻の質出し・賃借り出産までありました、などという、ずいぶんな父系社会だった中国においてこの母系社会集団は珍しい。 おかげで、家庭は全く平和そのもの。暴力沙汰もなしに、みな毎日幸せに母親のもとで暮らしている。当然女性の地位は高く、家長も女性。家は、母から娘へと代々引き継がれる。しかも昔はモソ語日常会話に、「父」という呼称すらなかったという(4)のだから、フェミニストが聞いて随喜の涙にもんどりうって溺死しそうな村だ。 男は、実の子供からも「お父さん」とは呼んでもらえず、他の男と一緒くたにして「阿鳥(アウ)」(おじさん)、などと呼ばれている。「お父さん」ではなくて、「おじさん」であるからには、即ち養育義務も道義的責任も、月々の支払いも一切ない事が明らかなわけで、これはこれでまた随喜の涙を流してしまうトンデモ男がいるかもしれないが、やはり父として、一人の男としては些か複雑な心境ではなかろうか。 「妻問い」の習慣があるのだから、『万葉集』や『常陸国風土記』に見られるような、照葉樹林文化的「歌垣」も大いに盛んだったら興をそそられるところなのだが、残念なことに、現地でフィールド・ワークをした遠藤織枝さんによると(5)、男女が夜集うものの、何やらフォークダンスみたいなものを一緒に踊って時々「ヤー」とか「ホイ」とか言うだけで、さほど面白いものではなかったらしい。でもまあ考えてみれば、気に入った女の子の手をとって適当に「ヤー」とか「ホイ」とか言っていればいいのだから、よほど見てくれの悪くない限り、私たちもこの宴に参加して、負けずに「ヤー」とか「ホイ」とか言い続けていれば、モソ人の素敵な恋人をつくれる可能性がある。 ところで、冒頭で多分に妄想だらけの「女人国」目指し船出した世之介、その後どうなっただろうか? 男ひでりの女たちを喜ばせてやろうと準備万端の世之介、はやる胸を押さえながら、怪しい性具満載の船に乗り込んだ。来年の還暦祝いにと無理やり贈られた赤いちゃんちゃんこ太平洋の碧き波間にびりびり破り捨てれば、心はうきうき、鼻歌はもれ、太鼓片手に足振り上げ、ほとんど甲板をひょっとこ踊りしながら行ったり来たりなどという状態になってしまい、船長が初めからこんな有様では船員としては航海にたいへん不安を覚えるものの、別に止める理由もないのでそのまま出航したのだが、たちまち海の彼方で、「行方(ゆきがた)知れずなりにけり」(井原西鶴『好色一代男』巻八「六十歳 床の責道具 女護の嶋わたりの事」)。 かわいそうに、どうやら勢いあまって、「風船おじさん」みたいな最後を遂げてしまったようである。 
|