以前当コラム(67)で紹介したドキュメンタリー映画『キャメラを持った男たち−関東大震災を撮る』(81分)が、9月1日の関東大震災100年にむけて、8月下旬から、東京・大阪・神戸・横浜・宮古などの映画館で上映が始まる。また7月開催の第25回ゆふいん映画祭への参加も決定した。この間、われわれもこの映画のパンフ・ポスター(デザイン:桜井雄一郎)の制作を手伝ってきた。
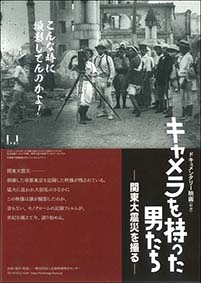
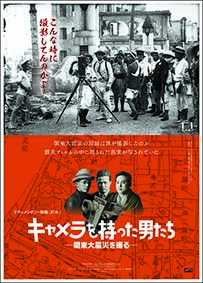
パンフ・表紙 ポスター
映画のホームページも立ち上がった。NY在住の平野共余子さんもすぐに映画評を寄せてくれた。
『キャメラを持った男たち』 平野共余子(映画史研究者)
炎が上がり逃げ場を探す人々の前で、3人のキャメラマンたちは何を思って撮影機を廻していたのだろうか。重い機材を担いて何時間も歩いて撮影をするという行動の動機は、何だったのか。前代未聞の体験を前に、記録を残さなければいけないという使命感からか。多くの死者を出したこの悲劇を繰り返さないためにも、記録を世に広く訴えたいというヒューマニズムか。映画の後半、撮影を生業とする柳田慎也氏は東日本大震災の津波を捕らえた自分の行為を無意識の行動であったように語っている。
しかし死臭漂う中に自らを置きながら「記録」という活動に携わることは、的確な構図を決めて目の前のイメージを効果的に捕らえる判断を下す客観性を要請される。どこを切り取ってレンズの中に収めるかを決めて行く主観の選択も迫られる。キャメラを構える男たちの頭の中で一瞬一瞬に選ばれて行った映像は、限りなく深淵な意味を問う。
関東大震災の記録の資料としての意義を彼らの映像から考察するとちぎあきらさん、撮影者たちが実際に歩いた道のりを検証する田中傑氏には目を開かれたが、さらに撮影者であった「男たち」の心情を解明する後世の同業者の「女たち」の一人、芦澤明子さんの登場に私は思わず拍手をした。もし21世紀の5分の1を過ぎた現在、未曾有の出来事を記録するのは「キャメラを持った女たち」でもあるはずだ。
(平野共余子:小社HPコラム「アンコウになって、闇より帰還」を連載中)
東京の両国駅の北に都立横網町公園がある。ここは100年前の関東大震災当時、旧被服廠跡(ひふくしょうあと)と呼ばれた空き地に4万人ともいわれる避難民が殺到した。そこに火を伴った竜巻「火災旋風」が発生し、3万8000人が死亡した。関東大震災死者・行方不明者が約10万5000人と言われるから、これは大変な数字だ。映画『キャメラを持った男たち』では、9月4日の旧被服廠跡に積み重ねられた死骸が写しだされている。大震災後7年の1930年、ここに「震災記念堂」ができ、さらに1951年には、太平洋戦争中の東京大空襲の犠牲者の遺骨も慰霊塔に納められ、合わせて約16万人の遺骨が安置されて「東京都慰霊堂」となった。公園内の一角には「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼の碑」がある。
ここでも8月に上映会が計画されている。
散逸していた関東大震災の記録映画20本からこの映画が生まれた。あたらめてフィルムアーカイブやアーキビストの働きが注目される。
参考サイト:
国立映画アーカイブ「関東大震災映像デジタルアーカイブ」
https://www.nfaj.go.jp/onlineservice/kanto1923/

