先日、山梨県北杜市の清里に行ってきた。2泊3日の旅だ。雪のことや路面凍結も心配だ。しかも我が老クルマはいっさいの冬仕様をしていないので、この時期は清里に行くことはいままで一度もなかった。実はどうしても会いたい方(犬ですが!)がいたのだ。いつもお世話になっているB&Bのバーネットヒルのご主人から年末に連絡があった。いろいろな縁があって、正月休み明けの6日に盲導犬(アイメイト)の引退(リタイア)犬を迎えることになったという。アイメイトは10歳から12歳になると、体調や体力の様子をみて、リタイア犬として使用者の親族、友人などが引き取るという。
イエローのラブラドール、女の子で名前は「スージー」という。どうしても会いに行きたいという家族の熱情(いや私もだが)に負けて、厳寒の山梨に行くことにした。ただ、天気のことが心配なので、まず電車で行く計画をたてた。しかしあらためて前日に様子を確認すると、積雪はなく当分の間は快晴が続くようなので、一大決心をしてこのままの車で出かけることにした。もちろん、今回もゴールデン・レトリバーのナイジェル(コラム62参照)にも会いに行く。
スージーは先週まで現役のアイメイトだった犬だ。8年の奉仕をしてきて、まもなく10歳なるが、体調は問題がなく、もちろん性格もすばらしい。すぐに新しいご主人になついたようだ。スージーは我が家のパル(2020年4月に14歳で死んだ。彼はアイメイトになれなかった不適格犬、アンフィットだ)に比べると、ひとまわり小さいが、ふたりは遠い親類にちがいない、本当によく似ている。スージーの日常はバーネットヒルのサイトでご覧になれる。毎日、毎日と、清里の自然と生活に溶け込み、先住の2匹の猫ちゃんとの距離も縮まってきている。
あのナイジェルも生後9ヶ月を迎え、またまた大きくなり、力強くなっていた。
★
バーネットヒルをチェックアウトする際、ご主人からここの図書室にある2冊の本をお借りした。清里の歴史をもう少し知りたかったのだ。
『清里――燃え尽きた原野』奈良靖夫著、あすなろ社、1981年
序文に「男子一生の本懐」(作家・杉浦明平)「ひたむきに生きる男の記録」(農業評論家・日野水一郎)の2本が入る。本書は「朝あけの章」「黄昏の章」の2部構成の半世紀にわたる酪農(ご自身は「牛飼い」という)の回想記だ。杉浦明平についての説明は不要だろう。
日野水(ひのみず)一郎は、東京帝国大学法学部を出た後、農林省の役人になる。本省課長を辞職して、1950年清里村の隣にある大泉村に入植し、「日野水牧場」を開いた人だ。奈良と日野水はいわば谷をへだてて付き合う隣りの村同志の牛飼い仲間だ。
奈良は大学卒業の半年後、1954年9月、清里村の朝日ヶ丘(当時は念場ケ原)に入植し、酪農を始めた。そこは「茅と熊笹と雑木の茫々たる原野」(奈良『清里』)だった。情熱と希望に燃え、日本農業の未来に貢献するという強い志を持った奈良の牧場経営は軌道にのり、手塩にかけた牛(ホルスタイン)も数々の賞に輝く。しかし、高度経済成長期の清里観光バブル、あの清里ブームによる地価上昇を契機に、周囲の農民は次々に土地を手放す。また農産物生産調整の目的で設けられた休耕奨励金制度はそれに追い打ちをかけ、休耕地は増え、酪農地帯としての清里はまるで急坂を転がり落ちるようにその凋落がはじまる。それが本書『清里』の「朝あけの章」「黄昏の章」の要旨だ。
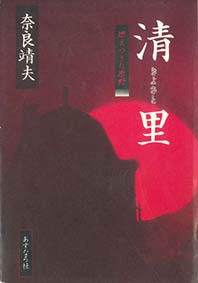
カバー 夕日に沈む「奈良牧場」のサイロ(写真:竹内敏信)
現在、奈良牧場は
ないが、このサイロはいまも残っている
『清里昭和史散歩』奈良靖夫著、朝日新聞東京本社朝日出版サービス、1992年
前書の刊行から10年後に刊行された自費出版の本。巻末には「奈良さんが命を賭けた1冊――あとがきにかえて」(朝日新聞社会部・加藤明)。加藤は『清里――燃え尽きた原野』が出版された際、朝日新聞甲府支局員として、奈良に取材している。奈良は1992年3月27日、清里の自宅で死去。がんで闘病中だった。享年62。本書はその翌月の4月6日に出版された。奈良は最期まで原稿を推敲していたという。巻末には「清里史年表」(47頁:1875年[明治8]~1989年[昭和64])があり、これは貴重な資料だ。
奈良さんのこの2冊の本を読んでいるうちに、清里開拓の本がもう1冊あることを知り、近くの図書館から借り出した。
『清里開拓物語――感激の至情、楽土を開く』岩崎正吾著、山梨ふるさと文庫(発売=
星雲社)、1988年
この3冊から、清里の歴史を学ぶ。
清里の歴史には、ふたりの主役がいる。ひとりは、清泉寮を作ったポール・ラッシュ(1897~1979)である。もうひとりはもちろん開拓農民たちである。今回は開拓農民の歴史に焦点をあててみたい。
中央自動車道の須玉(すたま)インターを降り、国道141号線に入る。通称「佐久甲州街道」あるいは「清里ライン」と呼ばれ、昔は「佐久往還」といったという。いまはバイパスの新道だ。小手指の坂をのぼり、高根あたりから旧道と合流、長坂の集落を過ぎ、左手に川俣川に架かる八ヶ岳高原大橋が見えると、弘法坂だ。この急坂を登りきると、広い清里高原がひろがる。このあたり一帯を念場ケ原(ねんばがはら)といった。小海線の清里駅ももうすぐだ。
1938年(昭和13)4月17日午前10時50分、28名の農民たちが清里駅に下車した。小海線は1935年に全線開通していた。かれらは山梨県北都留郡丹波山(たばやま)村鴨沢(かもさわ)地区の26戸、小菅村金風呂(かなぶろ)地区の1戸、東京府西多摩郡小河内村の1戸からなる、農民家族の入植先発隊だった。1930年から計画が立案され、ようやく前年の1937年から始まった小河内Fダム建設。ダムによってできる湖により彼らの家屋は水没することになり、この地に移転入植を決めたのだ。農民たちを中央線の甲府駅で出迎え、小淵沢駅経由で清里まで付き添って案内したのは安池興男(やすいけ・おきお 1904~1983)だった。安池は京都帝大農学部を卒業後、1936年に山梨経済部耕地課技師となり、同年の夏に山梨県八ヶ岳山麓開墾事務所長になっていた。
丹波山村は標高500メートル、ここ清里は標高1200メートルの高地。風土もちがい、炭焼きと養蚕しか知らない彼らには、原野の開墾や耕作の知識も経験もなかった。それにクマザサの生い茂る荒地。しかも水源に乏しく、火山灰による酸性度の強い土壌だ。安池は自身の生活や出世を顧みず、時には寝食を共にするまでして入植した28戸62人を心から支え、農業作付けや分教場の建設などを指導した。ここに「八ヶ岳開拓部落」が誕生したのだ。
5年後、安池は奈良県耕地課長に転任。1946年に退官し、故郷の静岡市に帰る。しかし、ここからまた安池と「八ヶ岳開拓部落」との交流が復活する。八ヶ岳区民は安池個人から肥料購入資金などで、何度も費用を借りる。開拓部落内に公民館が完成したのは1980年、その名も安池興男の功績をたたえ、「八ヶ岳興民館」と名付けられた。1981年には開拓部落内に共同墓地を作る。「感激の至情 楽土を開く」は、その共同墓地にある墓碑面に刻まれた安池興男自身の言葉だ。安池は1983年2月1日に死去、享年79だった。
ところで、「八ヶ岳開拓部落」の農民を故郷から追い出した小河内ダムはその後どうなっていたのだろうか。東京市が上水道用の貯水池を小河内村に設置することを決定したのは、1932年(昭和7)だが、なかなか建設は進まない。ようやく川崎市と東京市が妥協して、調印したのは1936年(昭和11)3月のことだ。この間の地元民の苦悩する姿をルポ風な小説にした石川達三の『日蔭の村』が刊行されたのは、翌年の7月だ。1938年(昭和13)4月、丹波山村、小菅村、小河内村からの先発隊が清里に向かい、7月から開拓地の区画割りをし、家の建設が始まる。ダムの工事は、その年の11月にようやく始まった。
しかし、1943年(昭和18)10月には太平洋戦争の戦況悪化で工事は中断、再開したのは敗戦後の1948年(昭和23)9月。「小河内ダム」(湖名は「小河内貯水池」から「奥多摩湖」に)が完成したのは、なんと1957年(昭和32)11月26日だ。丹波山村102戸、小菅村15戸、小河内村532戸が水没のため移転したという。「八ヶ岳開拓部落」が生まれてから、実に19年後のことだった。
★
3冊の本を中心に清里の歴史を学んできたが、わからないことが多い。1938年(昭和13)4月17日に清里駅に下車した28名の農民たちは、甲府駅で八ヶ岳山麓開墾事務所長の安池興男に出迎えられたが、かれらは丹波山村、小菅村、小河内村から、それぞれどのように来たのだろう。大菩薩峠の横を通り塩山駅に出たのか、松姫峠を越えて大月駅に出たのか、あるいはむしろ近いと思われた青梅駅まで行き、立川駅、八王子駅回りで甲府駅まで行ったのだろうか。また清里開拓本隊は家財道具だけでなく、先祖の墓石まで持ってきたという。どのコースで、どうやってきたのだろうか。清里開拓歴史ロードはまだまだ入り口だ。
参考文献:
『土とふるさとの文学』第7巻「記録の目と心」、石川達三『日蔭の村』収録(家の光協
会、1976)
『感激の至情 楽土を拓く――安池興男』(安池得之、1982)
『八ヶ岳山麓念場ケ原開拓の足跡』(安池興男著、発行者=酒井久重、1978)
「キープ協会史点描(1)清里一帯の開拓と入植者」松平信久
https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main...
初出は『立教学院史研究』(2019年、第16号)。清里の開拓史を丁寧に描写している。松平信久(1941〜2021)は立教大学名誉教授。

