関西在住の鵜飼雅則さんという未知の方から読書カードをいただいた。71歳、無職、男性とあった。購入してくださった書名は『未来へ 原爆の図丸木美術館作業日誌2011―2016』(岡村幸宣著、2020年)。この本は『新宿書房往来記』(港の人、2021年)を読んで注文して下さったとのこと。しかし、愛読者カードの小社の住所が旧住所だったうえ、移転後1年を過ぎていたため転送もされずに、ご本人に返送されてきたという。そのため、鵜飼さんは新宿書房の新住所を調べ、再度愛読書カードと感想のハガキそして資料やチラシも合わせてここに送ってくださった。
資料の中に『カンテラ』第1号、第5号、第6号があった。同誌は「炭都三池文化研究会」という団体の会報だ。同誌から、この5年の間にさまざまな[炭都三池文化の記憶と記録]の展示会が行われてきたことを初めて知った。創刊第1号は2020年3月14日で、発行元の「炭都三池文化研究会」は、2017年の5月から6月にかけて大阪で開催された「炭鉱の記憶と関西――三池炭鉱閉山20年展」をきっかけに誕生したという。鵜飼さんは1964年(昭和39)8月、父親が転勤で大阪に移るまでの14年間、大牟田の町で育った。
九州の大牟田にあった三井三池炭鉱(三池炭鉱)が長い歴史を終えて閉山したのは、1997年3月30日、それから20年が過ぎた。鵜飼さんは同展の3部構成のうちの「炭都と文化――昭和30年代の大牟田」を担当した。
それにしてもなぜ大阪で「炭鉱の記憶と関西」展が開催されたのか?関西には、九州の産炭地から離れ仕事を求めて移住した人々やその家族が十数万人いるという。閉山によって大量の失業者が生まれ、店を閉めた商店の人々や生徒数が激減した学校の教員といった人々もいた。三池炭鉱があった福岡県大牟田市や熊本県荒尾市に暮らした市民、それに炭鉱に関心をもつ関西在住のボランティアたちが、2014年に「関西・炭鉱と記憶の会」を立ち上げたのだ。
この会の中心になったひとりが、滋賀県彦根市に住む前川俊行さん。前川さんの父親は1960年の三池闘争で解雇された三池労組員。前川さんが小学校2年生の時に、一家は関西に来た。前川さんは、三池の記録を残したいと1997年から『異風者からの通信』を発信している。異風者(いひゅうもん)とは、熊本弁でいう風変わりな人という意味だそうだ。「いまどき、炭鉱の暮らしを懐かしむなんて変わり者というしかない。それでも三池にこだわりたい」という。
『カンテラ』第1号にはこんなくだりがある。「……これまで、三池の近代化遺産や労働運動の歴史、炭じん爆発事故などについては多くの考察がなされ書籍なども出ていますが、こと“文化”という視点からの考察はほとんどなされてこなかったと思います。……」たしかに同じ福岡県の産炭地・筑豊の中小炭鉱の町には、記録作家・上野英信や炭鉱絵師・山本作兵衛がいる。そして上野や工作者・谷川雁と森崎和江らの『サークル村』があって、東京の知識人からも注目されてきた。かたや三池は「文化不毛の地」のような評価がされてきた。あらためて「文化」という切り口から、三池の地層の暗闇にカンテラを提げて、その忘れられた文化の鉱脈を掘り起こそうとしてきたのが、「炭都三池文化研究会」なのだ。
「炭鉱の記憶と関西――三池炭鉱閉山20年展」
2017年5月5日~9日 エル・おおさか
2017年6月6日~30日 関西大学博物館
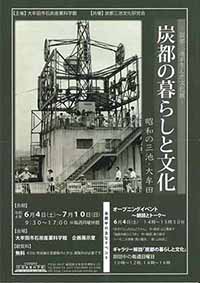
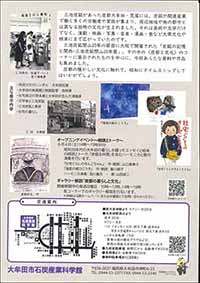
チラシ(表・裏)
「炭都の暮らしと文化――昭和の三池・大牟田」
2022年6月4日~7月10日 大牟田市石炭産業科学館
さて、最新号の『カンテラ』(第6号、2022年10月1日)に、注目すべき論考が掲載されている。鵜飼雅則さんの「松屋で開催された〈原爆の図展〉」だ。鵜飼さんは、大牟田市立図書館に収蔵されている地元新聞『大牟田文化通信』の中に1952年(昭和27)に大牟田の松屋デパートで開催された「原爆の図展」の記事があることを発見する。記事は3つあった。紙面の一部の画像を出しながら、その解説が進む。

『カンテラ』6号 表紙
1)11月1日付「赤松、丸木両画伯『原爆の図』九州に来る 各地にて大盛況」「大牟田には11月27日より30日までを予定してあるが、若松、筑豊、八幡では既に成功裡に幕を閉じた模様である」
2)11月11日付「『原爆の図』展を全市民のものに 大地評、映演協など五十余団体で 市長、教育委も後援」「十日より長崎、十六日より佐世保、二十二日より久留米の順で、大牟田は二十八日より四日間開催される予定である……」
3)11月21日付「原爆図展 全市的な催しにまでに発展 松屋六階にて二十八日より開幕」松屋とは、1937年(昭和12)に開店した百貨店大牟田松屋で、大牟田のシンボルだった。2004年に閉店、2009年には旧店舗は解体された。その松屋デパート6階のホールで原爆図展は開催された。
鵜飼さんは、ここで『《原爆の図》全国巡回 占領下、100万人が観た!』(岡村幸宣著、新宿書房、2015年)を引用する。2人の若者(ヨシダ・ヨシエと野々下徹)が「原爆の図」の再制作版を軸物に仕立て、木箱に収め背負って九州に向かう。およそ1年をかけた西日本巡回展の一環として大牟田開催があったのだ。しかし、『《原爆の図》全国巡回』では、この大牟田展のことがほとんど説明されてない。同書の巻末にある「丸木位里・赤松俊子《原爆の図》国内巡回展の記録(1950年~1953年)」では、1952年に「12(5日間)福岡県大牟田市 来場者27000人/[野々下メモ]」とあるばかりなのだ。鵜飼さんが発見した『大牟田文化通信』の記事から大牟田展の開催前のことがわかるようになった。しかも鵜飼さんは「『大牟田文化通信』の記事に拠る限り、大牟田での開催は十一月二十八日から四日間(もしくは延長され五日間)ではないかと思います」という。また、最後に「今回は当日の開催の模様を報じた地元紙の調査までには至りませんでした。後日を期したいと思います。」と結ばれている。
★
原爆の図丸木美術館の岡村幸宣さんに、すぐさま『カンテラ』6号のコピーを送ったところ、これはすでに手にされているようだった。それから間もなくして岡村さんから「福岡市の中西徹さんという方より、佐世保展の調査レポートが送られてきました」とメールがあった。1952年11月16日~19日まで開催された「原爆の図」佐世保展のことだ。中西さんの調査レポートのタイトルは「七〇年間、沈黙していた『原爆の図』の記憶――佐世保展の八十六人の感想文を発掘」(2022年11月3日記)。中西さんは『カンテラ』6号(2022年10月1日発行)掲載の鵜飼さんの発表論文に、すぐさま触発されたようだ。佐世保展は佐世保市公会堂で開催された。同展では「原爆の図展アンケート」を実施し、これから86人のアンケート(感想文)が抜粋され、これが佐世保文化研究会の発行する郷土誌『虹』第7号(1953年2月)に収録されていていたのだ。
岡村さんの『《原爆の図》全国巡回』が刊行されてから7年がたつ。読み継がれながら、資料・記録の空白を埋める作業・研究が続くとは、著者や編集者にとってこれほどうれしいことはない。鵜飼さん、中西さんに続く、「原爆の図」全国巡回の発掘の旅はまだまだ終わらない。

