今日も図書館へ。歩行はまだ
先日、原爆の図丸木美術館の岡村幸宣さんから教えてもらった本である。『つば広の帽子をかぶって いわさきちひろ伝』(飯沢匡・黒柳徹子共著、講談社文庫、1992年)。飯沢匡(1909~94)、黒柳徹子(1933~)、このふたりの著者、いまさら説明することもないだろう。ふたりが、いわさきちひろ(1918~74)と生前にどのような付き合いがあったかどうかはわからない。本書は、講談社の月刊PR誌『本』において同名のタイトルで1988年から89年にかけて連載され、1989年7月に単行本として刊行、そして92年9月に文庫化された。
第1章のタイトルは「〈甘い絵〉といわれながら」だ。この中で、飯沢は言う。「ここに、いわさきちひろの評伝をまとめるのは、一見甘美に見える〈ちひろ〉の作品にも、日本の国に生を受け、第二次大戦を経験し、そして画家として、また女性として、自立していった一人の日本女性の歴史――苦渋に充ちた生活があり、闘いがあったことを書きつけたいからである。」
構成は飯沢が評伝体で書き、黒柳が関係者の談話をとり、これらを交互に入れ子のように併載して物語が展開される。そのことによって「一つの今までなかった伝記にしようと考えた。」(飯沢)
飯沢は、ちひろの死後1977年に開設された「いわさきちひろ絵本美術館」(後に「ちひろ美術館」、現「ちひろ美術館・東京」、練馬区下石神井)の初代館長をつとめ、飯沢の死後は、黒柳が2代目館長となる。実は、同じ版元の講談社から、黒柳徹子は1981年3月に『窓ぎわのトットちゃん』を刊行している。これが700万部(現在は国内800万部、世界2317万部といわれる)を超える大ベストセラーとなった。黒柳が講談社の女性誌『若い女性』に2年間連載した自伝的物語だ。黒柳はちひろとは生前面識がなかったが、ちひろ絵本の大ファンだった。黒柳はみずから「いわさきちひろ絵本美術館」に出向き、ちひろが残した8000枚の絵から選んで連載の挿絵につかったという。初版は2万部、定価は1000円だった。この大ベストセラーによって、いわさきちひろは死後7年たって、新しい作品世界とファンの層を獲得したことはまちがいない。
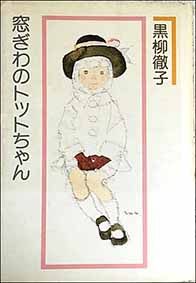
カバー表
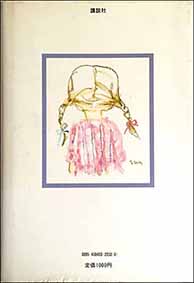
カバー裏
『つば広の帽子をかぶって いわさきちひろ伝』は、この大ベストセラーから生まれた企画だ。飯沢は言う。「私の意図はいわさきちひろの自立というところに焦点を合わせてみたいと思う。」1939年20歳の岩崎知弘(いわさきちひろ)は婿養子を迎え、結婚。夫の勤務地の満州大連に向かう。1940年、夫の自殺により、帰国。1945年5月、空襲で中野の家が焼かれ、母の実家のある松本市に疎開。秋には両親が長野県北安曇野郡松川村で開拓を始める。46年、日本共産党に入党、その春に単身上京する。ちひろ、27歳の春だ。戦中戦後の、実に重い7年間だ。同書の第10章「薄れゆく事実」、第11章「上京第一夜の謎を解く」、第12章「赤松俊子との出会い」*はたいへん興味深いところだ。
ちひろは上京した日、まっさきに人民新聞社編集長の江森盛弥をたずねる。その縁で丸木位里・赤松俊子(丸木俊)夫妻の世話**になる。1950年、ちひろ、松本善明と結婚。ちひろ31歳、善明23歳。善明は弁護士を目指していた。
部分的核実験停止条約の評価をめぐって、1964年6月、丸木夫妻は、朝倉摂、佐多稲子らとともに日本共産党本部に意見書を提出、11月には日本共産党から除名処分を受けた。このことで家族同様の付き合いをしていた丸木夫妻とちひろ・善明夫妻は交流を絶つことになる。しかも、松本善明は1967年の総選挙では東京都第4区(渋谷・中野・杉並)で日本共産党から立候補して初当選している。丸木夫妻はちひろの葬儀(1974年)にも、迷惑がかかるからと言って行かなかったという。
★
さて、いわさきちひろの技法(水彩によるたらし込み)については、赤松俊子(丸木俊 1912~2000)の影響を指摘する人も多い。この『つば広の帽子をかぶって いわさきちひろ伝』の著者の飯沢もそうだ。先日、ドキュメンタリー映画『いわさきちひろ~27歳の旅立ち』(2012、監督=海南友子)を見ることができた。このなかで、ちひろの技法について再現・解説している場面がある。たぶん、「ちひろ美術館・東京」のサイトにある「ちひろの技法について」と同じ映像資料かと思われる。これを見ても、わたしには日本画家の丸木位里(1901~95)の影響が強いような気がする。2008年に富山水墨美術館で開催された「いわさきちひろ展」では丸木位里の水墨画も出品されている。また2018年に東京ステーションギャラリーで「生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。」展が開かれ、ここでもちひろの「にじみ」や「ボカシ」の世界が展開された。さらに2008年から2009年にかけて、ちひろ美術館・東京で開催された「ちひろ生誕90年記念展 ちひろと水墨」では、丸木位里の水墨画もあわせて展示され、「丸木位里からの影響」を明確に指摘している。2020年の丸木位里の展覧会「墨は流すもの 丸木位里の宇宙」では位里の水墨世界を垣間見ることができる。
*『つば広の帽子をかぶって いわさきちひろ伝』は、『いわさきちひろ––––知られざる愛の生涯』と改題・再編集され、1999年4月に講談社+α文庫の1冊として出版された。カラー口絵8ページにはちひろの絵8点が収められている。旧版の第10章「薄れゆく事実」、第11章「上京第一夜の謎を解く」、第12章「赤松俊子との出会い」は、第10章「上京第一夜の謎を解く」、第11章「赤松俊子との出会い」にまとまられた。
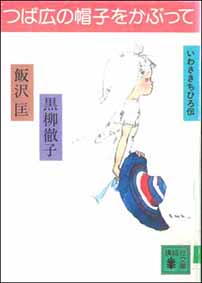
『つば広の帽子をかぶって いわさきちひろ伝』表紙
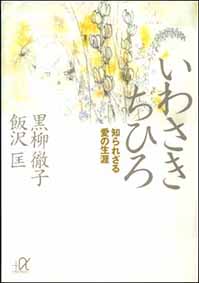
『いわさきちひろ––––知られざる愛の生涯』表紙
**『《原爆の図》全国巡回』(岡村幸宣著、新宿書房、2015年)には、《原爆の図》3部作が完成する前後の時代、1946年から50年にかけて池袋モンパルナス(桜ヶ丘パルテノン)や藤沢市片瀬の丸木夫妻宅での開かれたデッサン会に岩崎知弘(いわさきちひろ)が出入りする光景が描写されている。また丸木位里、赤松俊子のそれぞれの「裸体デッサン」(モデルは岩崎知弘)も掲載されている。

