はこだて
ある日、珍しい人から電話があった。大塚和義*さんだ。1941年生まれだから、今年81歳。声は昔と変わらない、ほんとうに若々しい。「春に都写美(東京都写真美術館)で開催された展覧会の図録を送るから」と言われる。
それは、『写真発祥地の原風景 幕末明治のはこだて』展といい、大塚さんは「第3章 はこだて鳥瞰」の中で「野口源之助の写真――近代日本初期のアイヌ生活風景を撮る」という文を寄稿しているという。
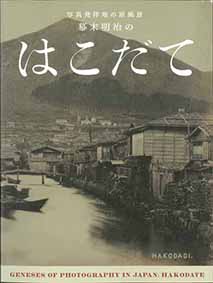
表紙
数日後にその図録がやってきた。図録には手紙と1枚の写真のコピーが挟まれていた。手紙には「……ここ数年がこれまでの蓄積を生かしきれるか不安ですが、数冊にまとめる予定です。生あるかぎり燃えつきるまでです」とあった。また、図録84頁の野口源之助《根室》(明治4年、鶏卵紙、大塚和義所蔵)の写真のコピーの余白にはこんな書き込みがあった。「根室県開拓判官松本十郎の部下たちとおもわれます。役人4人、アイヌの男1人、娘さん2人が撮られています。これを当時のアイヌ生活誌として解読したいとおもいます。」大塚さんはこれらの写真を、1990年初頭に東京神田の「古典籍展観大入札会」で入手したという。
私が大塚さんと最初に出会ったのは1972年ごろだろうか。平凡社の『百科年鑑』1975年版(各年版、前年の1年間の事象を記録する)から、独立項目「アイヌ問題」が登場し、執筆は大塚和義さん、編集担当は私だった。百科年鑑は1年間の政治・経済・社会・文化・科学などの事象を1000近い項目にして、「愛」から「ワルシャワ条約機構」までを五十音順に並べた1巻ものだ。「アイヌ問題」の項目は冒頭早くに登場する。しかし、大塚さんの原稿はいつも遅い、その言い訳も多々用意するという、締め切り遅刻の常習者だった。
原稿が入ると整理(原稿を徹底的手入れする)をし、校閲にまわす。そこでいろいろ疑問・質問が出て、これを解決すると印刷所にまわる。ワープロもない時代だが、電算写植だった。初校が出ると、今度は校正課に。基本、著者校正はない。一方、五十音順にその初校の棒ゲラを見開きのレイアウト用紙に貼って、最後までページアップしていく作業も始まる。本文だけでなく、写真や図版のコピーを貼っていく。項目本文のさまざまな赤字によって発生する行数の増減は、再校以降では各見開きのページの中で解決する。これを「仮貼り(かりばり)」作業と言っていた。本貼りに対して仮貼りだ。
仮貼りをする制作進行の先輩Tさんから、遅刻常連の「アイヌ問題」にはいつも文句がでていた。仮貼りが動かないのだ。ひどい時にはもらう原稿の予定行数の手形を切って、空白をうめてもらったこともあった。大塚さんの原稿締め切りに対する言い訳にはさまざまなストーリーがあったが、いまでも思い出す傑作がある。ある日、電話があった。「村山さん、原稿を昨日ようやく書き終えていたんだよ。ところが夕方、近くの屋台で飲んでいて読み直していたら、風が吹いてきて、全部飛んでいってしまったんです!」
しかし、毎年詳細な1ページ近い年表もついた「アイヌ問題」(1975年版~1980年版)の項目は、いま読んでも力作だ。
新宿書房では大塚和義さんの2冊の本を出している。
『草原と樹海の民』1988年(内モンゴル・北方少数民族誌紀行)
『アイヌ 海浜と水辺の民』1995年(日本の先住民族、アイヌ。アイヌ文化のダイナミズムを明らかにした書)*巻末の年表「アイヌの歴史」では、1998年改訂新版時に、1997年のアイヌ新法の施行にともない、北海道旧土人保護法(1899年制定)がようやく廃止された事実が加筆された。
*https://older.minpaku.ac.jp/aboutus/pe/ohtsuka/index
黒姫山荘ものがたり
8月31日、前日に急に思い立って東陽町に出かけることにした。参加者は3人。両膝の人工骨置換手術を4月22日に受けてから、家のまわりの散歩や自動車運転での外出をのぞいて、電車による遠出は初めてだ。同行のふたりによる見張りがたよりなる。午前10時半、地下鉄東西線東陽町駅の改札口に集合だ。自宅からJRの阿佐ヶ谷駅まではタクシー、そこから東西線で一本。外出での歩行ではずっと杖なしでがんばってきたが、電車なので杖を持参する。電車内ですばやく席を譲ってもらおうという魂胆だ。電車内にある交通弱者への優先席は、最近は屈強な男女がスマホをひたすらいじっていたり、あるいは寝ているふりをしている、そんな彼らに占拠されているので、杖は必要な小道具となる。
東陽町駅から向かったのは、竹中工務店東京本店1Fにある画廊のギャラリーエークワッド。
ここで「いわさきちひろと奥村まこと・生活と仕事」展が開かれている。画家・いわさきちひろ(1918~1974)と建築家・奥村まこと(1930~2016)のふたりの女性の生活と仕事を縦軸にし、ふたりが黒姫山荘の建築の際、施主(建築主)と建築家として出会い、その交流を横軸にした展示である。
展示の一番奥にスクリーンがあり、何人かの人が映像で証言をしていた。その中で、絵本作家の田島征三の話がとてもよかった。あの淡いタッチで描く子どもの絵に、ちひろは強い自信をもちながら、苦しんでいたのだ。
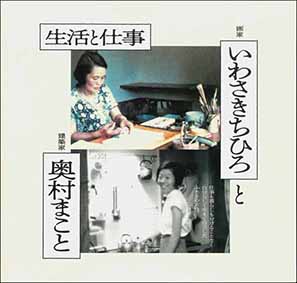
表紙
いわさきちひろの黒姫山荘は、1966年(昭和41)に、吉村順三設計事務所にいた奥村まことの設計で建てられた。まことは家具のデザインから施工管理、メンテナンスまでも手がけた。黒姫山荘の平面図などを見ると、施工者への細かい説明と配慮に驚く。
図録にある村上藍の「奥村まこと:生きることとつくること」がいい。まことは、自身のことを「町医者のような建築設計
黒姫の児童文化村を構想した仲間に児童文学者の岡野薫子(おかの・かおるこ)もいた。岡野薫子は科学映画の脚本家の仕事もしており、私の父(桜映画社創業者・村山英治)と親しかった。父が遺した本のなかに、岡野の著書『黒姫山つれづれ暦』(新潮社、1985年)があった。これをみると、児童文化村のことがおおよそわかる。
信濃町の町長から申し出のあった山荘用地は、信越本線柏原駅(1968年に黒姫駅に改称)から下りて妙高高原に向かう途中の黒姫高原にあった。一戸あたり約300坪、20戸分が用意され、さっそく「黒姫山荘の会」が作られた。メンバーを職業別にみると、作家2(いぬいとみこ、岡野薫子)、画家8(赤羽末吉、柿本幸造、川崎春彦、木川秀雄、山本まつ子、吉崎正巳、いわさきちひろ、他)、出版関係3、大学関係2、デザイナー1、医師3、その他1、とある。
同書にはこんなくだりがある。「いわさきちひろさんと私が初めて会ったのは、この山荘村であり、彼女が亡くなる前の年(引用者注=1973年)の夏だった。あの清楚な少女を描きだすちひろさんは、地味で素朴な感じの人だった。」ちひろが最晩年の頃だ。山荘仲間との交流はもうそんなになかったかもしれない。しかし、同時期に同じ長野県の御代田町で始まった芸術村「普賢山落」(当コラム(41))ほどの強い共同体意識は、ここ黒姫山荘の会にはなかったようだ。
いわさきちひろの黒姫山荘は、今は黒姫童話館&童話の森ギャラリー内に移築されている。

