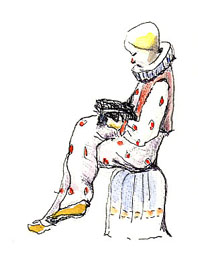 私が子どものときには、もちろんテレビなどなかった。兄弟のない私の、家での楽しみといえば、もっぱら読書であった。その本好きが、71歳の今日まで続いてきたことを、今、とても幸せに思っている。
私が子どものときには、もちろんテレビなどなかった。兄弟のない私の、家での楽しみといえば、もっぱら読書であった。その本好きが、71歳の今日まで続いてきたことを、今、とても幸せに思っている。
老年期を心豊かに過すには、人とのつながりがたいせつだ。しかし一方で、ひとり遊びもできなくてはならないと思う。私にとってそのひとつが読書なのだ。
タイトルと著者名だけを、手帖につけることにしていて、それによると、ここ数年は毎年、80冊あまりの本を読んでいる。老眼の身としては、なかなかの数なのではないか。いや、若者は本ばなれしていると聞くから、本に親しんでいるのはむしろ老人側なのかもしれない。
四年前には119冊読んでいる。これは私が入院生活を送ったからだ。
肺の一部切除手術を受けたのだが、そういうときには、当然ながら死とむきあうことになる。通夜の客が集まることになるかもしれないと、わが家の畳替えをすませ、また、丸坊主を予測して、スカーフの用意もして入院した。幸いそうならなくてすんだけれども。
クリスチャンの友人がいて、かねがね、聖書を少しは読んでいた。こういう機会に信仰の道が開けるのではないかと、その方面の本も何冊か持参した。私の選び方がまずかったのかもしれないが、それらは重くきびしすぎて、弱った心身が受けつけなかった。
いちばん愛読したのは、遠藤周作の文庫本である。病気を体験してきた人の言葉は、素直に心に入ってきた。しかも明るくユーモアがあるので救われた。
読み進んでいくうちに、まあこれはこれでしようがないやと、自分の状態を認めることができるようになった。そして、どうせなら、死に上手になってやろうやないのと思えてきた。本のおかげである。
ところで出版社さんには申しわけないが、それだけの数の本を、いつも新刊書で買っているわけではない。月に一度、わが家のすぐ近くの公園へ、移動図書館バスがやってくる。これは公営で、満載されている本から8冊まで、無料で借り出すことができる。気楽に選んで帰り、さて何頁か読みだしてから、ああ
これは前に借りた本と同じだと気がつく失敗もある。しかしさまざまな本にふれることができるのは、とてもありがたい。
そういうふうにして村上龍の『希望の国のエクソダス』という本を読んだ。
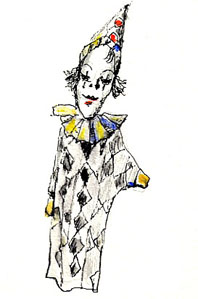 実はその本を読む少し前に、私の孫の一人が、高校を退学したと連絡を受けていたのである。
実はその本を読む少し前に、私の孫の一人が、高校を退学したと連絡を受けていたのである。
不登校問題はしばしば報道されていたけれども、自分の身内におこるとは思ってもみなかった。遠く離れて暮らしていて、電話で説明してもらっても、納得がいかない。
小説は、政治的にも経済的にも崩壊寸前の日本が舞台で、これはフィクションながら、真に迫っていた。そして不登校の中学生たちが集団になって、得意のコンピューターをあやつり、莫大な資金を得て、新天地を建設するというのである。
読み終えて、今の社会の変化が、不登校の若者たちの心情が、私に理解できたわけではない。しかし、昔の価値基準のまま、あれこれ判断するのがよくないことだけはわかった。
わからなくてもしようがないではないか。わかったふりをせず、なるべく柔軟な心になって、変化を見つめることにしよう。孫の成長を祈っていることにしよう。そう思えてくると心が安らいできた。本のおかげであった。
先日新聞に、チェーホフの晩年の手紙文が紹介されていた。
ごきげんよう。なによりも快活でいらっしゃいますように。人生をあまりむずかしく考えてはいけません。おそらくほんとうはもっとずっと簡単なものなのでしょうから・・・
この言葉が、妙に、いつまでも心に残っている。次はチェーホフを読んでみようか。できたらその手紙も。
かくして本好きの幸せは続いていくわけーーーー。

