「待ったなしの事業継承!後継者不在にお悩みの経営者様へ」「ヒキツグ ハッピーエンドを、見つけに行こう。浸透する事業引き継ぎ」「事業継承でお悩みの方へ」などの文字が踊るDMが最近しきりに事務所に送られてくる。いや、どうしてもそこに目がいってしまう自分が情けない。経済産業省や東京商工会議所、中小企業庁などから送られてくる、綺麗にデザインされたパンプレットだ。これらも官庁から某大手広告代理店に丸投げされたキャンペーン事業の仕業かもしれない(笑)。しかし、出版社の休廃業のリアルな話は仲間からもたびたび耳にすることが多く、もはや他人事ではない。
そんな折り、『朝日新聞』8月26日の夕刊に「解散出版社の学術書 他社が継承」と題する記事が出た。調べてみると、『東京新聞』(7月2日)や『日本経済新聞』(7月11日)などの他紙もすでに報道している。これは、1951年に創業し70年間で1800点の本を出版してきた学術書専門出版社の創文社(そうぶんしゃ)が、2020年6月30日をもって解散したという記事だ。しかし同社の全書籍は絶版をまぬがれ、他の出版社が引き継ぎことになった。なくなる出版社が残した本を他社がまとまった形で引き継ぐことは異例だという。
このうち1985年から刊行中の『ハイデッカー全集』(全103巻)はまだ予定巻数の半分しか刊行してなかったが、この全集は東京大学出版会が引き継ぐという。
また講談社は、創文社の刊行した書籍うち、すでに他の版元に移っていたものや、著作権利者が不明なものを除き、すべての書籍を引き取った。その中には、創文社が実に52年もかけて翻訳してきた神学者トマス・アクィナスの『神学大全』(全45巻)など、1500点以上があるという。
講談社はこれらを「創文社POD叢書」(仮称)シリーズとして刊行する。PODは「プリント・オンデマンド」出版(オンデマンド印刷ともよばれる、デジタル印刷の総称)のことで、読者から注文があれば、そのつど製本して本を届けるという。
弘文堂(こうぶんどう)というたいへん歴史ある出版社がある。1951年、弘文堂のふたりの社員が独立してそれぞれの出版社を始めた。それが、未来社(西谷能雄)と創文社(久保井理津男)だ。
大学時代の私にとって創文社とはマックス・ウェーバーの著作を数多く出している出版社だった。1978年ごろか、平凡社に近い千代田区一番町のお屋敷町にあった、それは広い敷地に建つ古い洋館の創文社に本を買いに行ったことがあった。大きな玄関を入り声を掛けると、奥から品のいい初老の女性が出てきた。創文社では学術書のほかに、山の文芸雑誌『アルプ』も出していた。雑誌『アルプ』は尾崎喜八と串田孫一を責任編集者にして、1958年に創刊され、1983年に300号をもって休刊している。私はその『アルプ』のバックナンバーを買いに行ったのだ。
池内紀は、「北のアルプ美術館」のコラムで、『アルプ』のことを次のように書いている。「山の雑誌だが、山の案内はしない。コース紹介、技術や用具をめぐる実用記事といったものもまるでなし。広告は一切のせない。そんな雑誌が300号つづいた。わが国のジャーナリズムにあって、とびきり大胆で、きわめて珍しいケースだったのではあるまいか。」
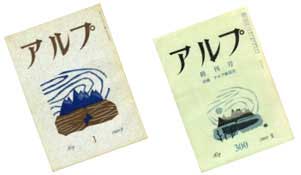
ある出版社(そして編集者)が終わる時、残された本たちの行方はどうなるか。創文社の本のような運命は確かに珍しいし、美しい話だ。いくつかの消えたえユニークな出版社を思いおこす。社会思想社、リブロポート、おうふう(桜楓社)、弥生書房、北斗出版、思索社(新思索社)、どうぶつ社、小沢書店・・・。それぞれの出版社の本たちはいまどこにいるのか。
社会思想社には「現代教養文庫」というのがあった。現代教養文庫でよく売れた本や腕力ある著者の本は、他社の衣を着た本となって第二の人生を歩んでいる。リブロポートには、「シリーズ日本の民間学」というのがあったが、めぼしい本は他社で増補版として蘇生している。
消えた出版社の本の多くは、バラバラにされ他社の文庫、新書、双書の企画のいわば草刈り場となってきていた。創文社の創業者・久保井理津男は「良書は一人歩きする」という言葉を残したそうだ(前掲『東京新聞』)。確かに「良書」というものは、さまざまな編集者、解説者に再発見され、版元を代え生まれ変わって、何度も新しい読者に迎えられてきている。消えた出版社にいた編集者が自分のやってきた企画を手土産に他社に移ることも多い。そして新天地で本はまた生まれ変わる。本とひと(編集者)が一緒に旅をしてきたのが、いままでの出版界かもしれない。
今回の創文社の本の行方。PODは消えた出版社の本の運命を、これから大きく変える事件かもしれない。

