猛母を通じて社会を描く
11月末、NYのルーマニア映画祭の季節がめぐってきた。今年(2013)で8回目の「Making Waves: New Romanian Cinema(波を起こす・新しいルーマニア映画)」、今回はリンカーン・センターのほか、NY郊外のジェイコブ・バーン・センターでも開催された。
今年の目玉はベルリン映画祭の最高賞である金熊賞を受賞し、アメリカの配給も決まったカリン・ピーター・ネツアー監督の『子供の姿勢(Child’s  Pose/Positia copilului)』だ。脚本は現代ルーマニアを代表するラズヴァン・ラザレスクとネツアー監督の共作。冒頭、疎遠になった一人息子への不満を、女友達に延々と喋るヒロインのコーネリア(ルーマニアを代表する女優ルミニツア・ゲオルギウ)を捕らえるカメラが、彼女の動きと対応してひっきりなしに動き、不安で定まらない彼女の心情を映し出す。建築家で舞台装置家の彼女は社会のエリートで、裕福な暮らしをしている。誕生日パーティを大臣などの有力者たちとレストランで祝うが、息子の姿はない。
Pose/Positia copilului)』だ。脚本は現代ルーマニアを代表するラズヴァン・ラザレスクとネツアー監督の共作。冒頭、疎遠になった一人息子への不満を、女友達に延々と喋るヒロインのコーネリア(ルーマニアを代表する女優ルミニツア・ゲオルギウ)を捕らえるカメラが、彼女の動きと対応してひっきりなしに動き、不安で定まらない彼女の心情を映し出す。建築家で舞台装置家の彼女は社会のエリートで、裕福な暮らしをしている。誕生日パーティを大臣などの有力者たちとレストランで祝うが、息子の姿はない。
ほどなく息子がブカレスト郊外で交通事故を起こし、14歳の少年が死亡した知らせをコーネリアは受け取る。そこから彼女の執念は、いかに息子を救うかということに賭けられる。スピード違反をしていたと認めた息子の自白や証人の言を、友人や夫のコネ、財力を駆使して変えさせる。うんざりした夫が彼女の名前をもじって「コントローリア」と呼ぶように、彼女は周囲の人たちや状況を自分の思い通りにコントロールしなければ収まらないのだ。
慎ましい暮らしをしている被害者家族のことは全く意に介していなかった彼女が、気に入らない息子の嫁にショッキングな告白をされ、息子にも面と向かって造反され、被害者家族を前にして人間らしさを取り戻していくところで映画は終わる。まったく絶望的に駄目な人間と思われていた息子も、最後に人間らしさを証明する。
こうしたストーリーでは到底登場人物に同情できないのだが、クローズアップを多用した息苦しいようなカメラワークにより、観る者は至近距離でコーネリアの顔を見続け、彼女の表情の一喜一憂につきあわされる。しかも全編手持ちカメラで、彼女の揺れ動き続ける心情とともに、観るものの心情も振幅する。その結果、彼女も人間なのだという不思議な共感のようなものが観るものに沸いて来る。舞台出身のゲオルギウの演技は、すごいと膝をたたいてしまう見事さだ。それとともに、弟が家の建築許可で困っているから何とかしてくれないかとコーネリアに頼む刑事や、金次第で証言を変えるという目撃者など、こすい人間の行動を通して、腐敗した社会の現状が浮かび上がってくる。
映画監督の悩み
今やルーマニアを代表するコーネリウ・ポルンボイウ監督の新作『夕闇がブカレストを包む時 、あるいはメタボリズム(When Evening Falls on Bucharest or Metabolism/Cand se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism)』も今年の映画祭で上映された。主演の映画監督を演じたのは、前述『子供の姿勢』でヒロインの息子役を演じていたボグダン・ヂュミトラケである。夏のロカルノ映画祭、秋のトロント映画祭、ニューヨーク映画祭で上映され、アメリカの配給も決まっている。絶賛するアメリカの批評家も少なくない。ポルンボイウ監督の短編と前二作、『12時8分、ブカレストの東』と『警察・形容詞』も今回回顧上映された。前二作を高く評価する私には、新作にはいまいちのれなかった。非常に考え尽されたスタイルの映画で、男女が車内の運転席で映画についてのさまざまな会話をしているところを後ろから固定カメラでじっと撮っている長いショットから本作は始まる。次第にこの二人が映画監督と主演女優であることがわかる。古今東西の名画の例を出し、監督は現在製作中の映画の演出やデジタル映画とフィルムによる映画の比較などについての話をしている。
、あるいはメタボリズム(When Evening Falls on Bucharest or Metabolism/Cand se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism)』も今年の映画祭で上映された。主演の映画監督を演じたのは、前述『子供の姿勢』でヒロインの息子役を演じていたボグダン・ヂュミトラケである。夏のロカルノ映画祭、秋のトロント映画祭、ニューヨーク映画祭で上映され、アメリカの配給も決まっている。絶賛するアメリカの批評家も少なくない。ポルンボイウ監督の短編と前二作、『12時8分、ブカレストの東』と『警察・形容詞』も今回回顧上映された。前二作を高く評価する私には、新作にはいまいちのれなかった。非常に考え尽されたスタイルの映画で、男女が車内の運転席で映画についてのさまざまな会話をしているところを後ろから固定カメラでじっと撮っている長いショットから本作は始まる。次第にこの二人が映画監督と主演女優であることがわかる。古今東西の名画の例を出し、監督は現在製作中の映画の演出やデジタル映画とフィルムによる映画の比較などについての話をしている。
次はレストランで、この二人の会話が続く。ここに監督の友人の青年が一瞬テーブルに来て、また去っていく。このあたりで私は気持ちの良い眠りの世界に入っていき、気がつくと監督のアパートであった。監督が製作中の映画について苦吟している。そして女性の製作者を呼び、主演女優とリハーサルを何度もさせる。題名の「メタボリズム」というのもとうとう私には理解できないまま終わった。多くのアメリカの評が、映画製作を主題にしている本作を、韓国の監督で毎回映画監督とその周囲の学生をテーマにした作品を撮るホン・サンスと比していたが、私は最近ホン・サンスには毎回「またか」という思いを抱き、その狭い世界観をまったく買えない。ホン・サンスの映画にまつわる作品群もこのポルンボイウの作品も、映画製作というテーマを通じて、人間について、社会について、何か新しい発見をさせてくれたとは思えない。映画製作を舞台にした映画で傑作は、フランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』(73)ぐらいかとあらためて思った。
レッド・ウエスタン
今回この映画祭で紹介された興味深いジャンルは、1970年代から1980年代にかけて人気を博した“レッド・ウエスタン”である。これは共産主義の国の西部劇という意味だ。アメリカの西部を舞台にしていながら、ルー マニア人たちが大活躍するコミカルな活劇で、まさかアメリカまでロケに行けないのでルーマニア国内の山岳地帯で撮影している。「トランシルヴァニア人三部作」といわれる作品群の第一作『預言者、金、そしてトランシルヴァニア人たち(The Prophet, the Gold and the Transylvanians/Profetul, aurul si Ardelenii)』(1979年、ダン・ピツア監督は共産党支配下で社会批判的映画を作ったことでも有名。このコラム7号で、『石の婚礼』が紹介されている)を見たが、題名のつけ方からして、イタリアのマカロニ・ウエスタン的である。南北戦争終了後25年の1890年のユタ州、金鉱の利益を独り占めし、妻が15人、常に若い女性を狙う悪徳教祖が牛耳る町で、それに立ち上がる主人公ジョニー・ブランドは何と(というかこれはルーマニア映画なので)やはりルーマニア人イオンのアメリカ名であった。
マニア人たちが大活躍するコミカルな活劇で、まさかアメリカまでロケに行けないのでルーマニア国内の山岳地帯で撮影している。「トランシルヴァニア人三部作」といわれる作品群の第一作『預言者、金、そしてトランシルヴァニア人たち(The Prophet, the Gold and the Transylvanians/Profetul, aurul si Ardelenii)』(1979年、ダン・ピツア監督は共産党支配下で社会批判的映画を作ったことでも有名。このコラム7号で、『石の婚礼』が紹介されている)を見たが、題名のつけ方からして、イタリアのマカロニ・ウエスタン的である。南北戦争終了後25年の1890年のユタ州、金鉱の利益を独り占めし、妻が15人、常に若い女性を狙う悪徳教祖が牛耳る町で、それに立ち上がる主人公ジョニー・ブランドは何と(というかこれはルーマニア映画なので)やはりルーマニア人イオンのアメリカ名であった。
イオンを訪ねてその二人の兄弟がルーマニアから訪ねてくる汽車の中の場面で映画は始まる。若いロミは英語を勉強中で、山羊の毛皮をまとった巨漢トライアンは粗暴で英語などどこ吹く風だ。二人がわからない英語は、ロミの「辞書に載っていない」という言葉が繰り返されることも笑いの種となっている。近くに座る婦人は偏見丸出しで、あの人たちはインデイアンかメキシコ人だろうかといぶかっている。冒頭から、早くから来た移民のイギリス系白人を主体とするアメリカ人にとって、見慣れない習慣や風俗の「他者」に対する偏狭さへの風刺をしながら、スラップスティックな喜劇ともなっている。
遅れてきた移民への偏見というテーマは、1890年代のワイオミングを舞台に、後から到着した東欧系移民が先住牧場主たちに迫害された実話“ジョンソン群の戦争”を基にしたマイケル・チミノ監督の『天国の門』(80)が思い起こされる。同時に私は、アメリカ西部からオスマン・トルコの圧政下のマケドニアに渡り、敵味方となって戦う兄弟を描くミルチョ・マンチェフスキーの新旧大陸を横断する壮大な『ダスト』(01)にも思いを馳せた。
トライアンはトルコと戦ったのが誇りで、オーストリア=ハンガリー帝国下、オスマン・トルコに反乱することを許されなかったが愛国者である自分は勇敢に戦ったという台詞がある。そのような史実を私は知らなかったが、活劇映画のようなポピュラー・カルチャーで、自分たちのアイデンティティを保守した歴史に触れているのが興味深い。ルーマニア人、あるいはバルカン出身者たちがこの映画を観れば、さらにさまざまな隠喩を見出すのだろう。
アメリカ人批評家たちは、銃が支配する西部の金鉱とか新興宗教という、外国人から見たアメリカ歴史文化の神話の描き方に関心を持っていた。さらにこのモルモン教の独裁者の描き方は、チャウシェスク独裁下のルーマニアのアレゴリーではないかと言っている人もいた。イオンたちを助けるアメリカ人がいまだに南軍の制服を着ている誇り高き元将校だが、その部下だった拳銃の名手は教祖側に雇われている。このあたりのアメリカの描き方も興味深いが、あくまで主役はイオンで、大活躍するのはイオンとその兄弟である。
映画祭主催者の一人、オアナ・ラドュと話したら、この三部作の最後の作品はアメリカの西部でルーマニア人三兄弟がハンガリー移民と出会う場面があり、さらに興味深いそうだ。チャウシェスク政府の下では国内の少数民族の話題はタブーだったので、ルーマニア人が隣人のハンガリー人といがみ合ったり、アメリカ人という共通の敵を前に仲良くなったりする描写が、舞台をアメリカ、時間も過去のことに移したことで可能になった。公開当時とても人気があり、その後何度もTV放映もされているのでルーマニア人にとってはおなじみのこのシリーズも、実は何層ものいろいろな意味がしかけてあることを見つけて論ずることができるという。
家族離散のドキュメンタリー
家族離散についてのドキュメンタリー『ここ、いや、あそこ(Here… I Mean There/Aici… adica acolo)』は女性監督、ラウラ・カパツアナ=ユラーによる。 フランクフルトでジャーナリズムとメデイアを学んだ後ルーマニアのTVで働いていた彼女の処女作。以前、ルーマニアのモルドヴァ地方からイタリアに出稼ぎに行き、残された夫と幼い子供たちの農村生活を描くドキュメンタリー『花の橋』を見たが(このコラム9号で紹介している)、本作では幼い時に祖父母に預けられ、スペインに出稼ぎにいった父母を待つテイーンエジャーの姉妹を4年間にわたって描く。出稼ぎは、体制崩壊後のルーマニアによく見られる現象である。しかも前述のオアナによれば、モルドヴァでは女性が出稼ぎに行くことが普通で、家計を女が支えるので夫は劣等感を持ち、また別の問題が生じるという。
フランクフルトでジャーナリズムとメデイアを学んだ後ルーマニアのTVで働いていた彼女の処女作。以前、ルーマニアのモルドヴァ地方からイタリアに出稼ぎに行き、残された夫と幼い子供たちの農村生活を描くドキュメンタリー『花の橋』を見たが(このコラム9号で紹介している)、本作では幼い時に祖父母に預けられ、スペインに出稼ぎにいった父母を待つテイーンエジャーの姉妹を4年間にわたって描く。出稼ぎは、体制崩壊後のルーマニアによく見られる現象である。しかも前述のオアナによれば、モルドヴァでは女性が出稼ぎに行くことが普通で、家計を女が支えるので夫は劣等感を持ち、また別の問題が生じるという。
『ここ、いや、あそこ』の姉妹の滞在する祖父母の家は郊外にあり、隣に建てかけのレンガの家がある。両親が休暇で帰るごとに、手作りで建て続けているが、まだ外壁が整った程度である。両親は、この家を完成させることが夢で、出稼ぎに行っているのだ。
インターネット時代で、姉妹はたびたび両親とスカイプで会話をし、電話もかけあっているし、両親はしばしば段ボール箱いくつもの衣類を主体としたお土産をスペインから送ってくる。祖父母も愛情深く姉妹を育てているようだが、それでも両親不在の家庭は寂しく、姉妹は両親の帰宅を心待ちにしている。映画は全編、この二人の姉妹の視点から描かれている。両親が戻ると4人家族は近くの街に出て、買い物をしたりマクドナルドで食事をしたりする。それが本来の家族の姿だろうが、離れて暮らさざるを得ないルーマニアの庶民の経済状態が伺える。最後は、涙ながらに寂しさを訴える妹の姿が痛々しい。
創造的自由
「映画の創造的自由」と題されたパネル討論もあったので、行ってみた。共産党独裁体制の国々では、体制批判は検閲で禁止され、体制礼賛のプロパガンダ映画製作が強要されていた。このパネル討論では、ルーマニアだけでなくチェコからの参加も得て、討論に広がりがあった。ここで印象に残った発言を紹介しよう。
「一般にどの共産党政府も、共産党員のみがヒーローで人民を救う共産党礼賛の国威高揚映画を国内では積極的に作らせていたが、国際映画祭で評価される国際的な評判も必要だということがわかっていて、芸術的映画を作ることも容認していた。」(ルーマニアのナエ・カランフィル監督)
「チェコスロヴァキア国内では、軽喜劇が常に人気であった。アート映画の観客は今でも総計5万人ぐらいだろうか。」(チェコの20代の脚本家シュテパン・フリク)
「(ミロシュ・フォアマンなどの)チェコ派の映画はチェコスロヴァキア国内ではほとんど見ることができず、主に海外で見られていた。共産党政府が倒れてからすぐ、1990年に『スーパーマン』をチェコで見て、最後にスーパーマンがアメリカ国旗を手に空を飛ぶシーンを見て、ハリウッドにもプロパガンダが存在することを感じた。」(チェコの映画キューレター、イレナ・クジャロヴァ)
「ルーマニアが共産圏の中でチェウシェスクの下、特異なものであったということを、ルーマニアの映画史をひもといてあらためて認識した」(ルーマニア出身の映画史家、ドミニク・ナスタ)
「こうしたパネル討論もある種のプロパガンダだ。アメリカや西欧ではみな言論の自由があると信じているが、それは権力を脅かさない限りという条件付で、アメリカの“オキュパイ・ウオールストリート”の運動やイギリスの環境運動に過剰反応する権力側を見ればそれが判る。」(ルーマニアで映画を10数年撮っているイギリス人のトム・ウイルソン)
命題があまりに大きくて、全体的まとまりには欠けた討論だったが、上記のように個々の発言はおもしろかった。
期待されなかった奇跡
パネル討論に引き続き、ドミニク・ナスタの新著『現代ルーマニア映画―期待されなかった奇跡の歴史(Contemporary Romanian Cinema: The History of an 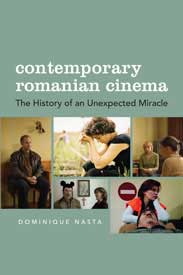 Unexpected Miracle』(コロンビア大学出版)が紹介されるプログラムにも行ってみた。ナスタはルーマニア生まれ、1984年、大学生の時に家族とともに祖母の出身地ベルギーに亡命し、彼の地で映画学の博士号を取得、ブルッセル芸術大学で映画学を講じている。
Unexpected Miracle』(コロンビア大学出版)が紹介されるプログラムにも行ってみた。ナスタはルーマニア生まれ、1984年、大学生の時に家族とともに祖母の出身地ベルギーに亡命し、彼の地で映画学の博士号を取得、ブルッセル芸術大学で映画学を講じている。
本著の副題の「期待されなかった」という意味は、海外では、ポーランド、チェコ、ハンガリー、旧ユーゴの映画は国際的に注目され高く評価されていたが、誰も注目していなかったルーマニアから2005年から2008年にかけて国際映画祭を凌駕する作品が次々と登場したという意味だそうだ。「ルーマニア・ニュー・ウエイブ」といわれるこの動きは突然登場したわけではなく、それに先行する歴史があるという彼女の主張に、私は全面的に賛成である。私が見ることができた独裁時代のルーマニア映画は20数本だが、それでも「こんな苛酷な体制の中、すごい映画が作られていた」と感嘆する作品が少なくなかったのだ。
ナスタは、独裁時代から芸術的な独自のスタイルを持った映画で国際的に知られるルシアン・ピンテイリエ監督は若い世代の心のよりどころであり、フランスのヌーヴェル・ヴァーグにとってのジャン・ルノワールのような存在だと語ったのは興味深かった。そしてナスタは続ける。クリステイ・ピウイ監督の『ラザレスクの死』を見たとき、その新鮮なパワーに圧倒されながら、ピウイの手持ちカメラの使い方は、ピンテイリエの映画の中の主人公の心理描写で使われていた手持ちカメラのスタイルなどのそれまでのルーマニア映画で見た手法だと思ったと。今のルーマニア映画にも多い手持ちカメラはなるほど、独裁時代の野心的作品に源を発していたらしい。
それでは、手持ちカメラの特徴は何だろうか。常に揺れる画像は、安心感を見る者に与えない。しかも即興性を重んじ、事前に用意したことだけでなく、目の前に展開する事象に敏感に、臨機応変に反応するスタイルだ。それはやはり全てを事前に統制する独裁制になじまないことが容易の想像できる。
国際的に評価が高い「ルーマニア・ニュー・ウエイブ」の成功の要因は、ほかの欧州の国から主要な動きがでてきていなかったこと、人間性に満ちた日常生活のリアリテイを描きながら、多様性に満ちた作品群であること、西欧ばかりから何かがいつも起こされてきたが、東欧から出てきた新しい動きであったことで注目された、と3つナスタは要因をあげた。
本書の中で、『4ヶ月3週間と2日』のクリスチャン・ムンジウ監督を「広範囲の現象」と定義していることについて観客からの質問に対して、著者のナスタは、映画キャンペーンをルーマニアの地方で実現するなどの戦略にも関わり、映画の作品を越えた存在といえるムンジウの特異性を挙げた。
今注目されるルーマニア映画について、ルーマニア語では本が何冊か刊行されているが、本著は英語では初めての本だという。まさに待望の著作である。私もその場で本を買い、ナスタ先生にサインしてもらった。早速読んでみたが、ルーマニアの歴史や文化に特有な事象、独裁制の政治制度と社会状況を丁寧に説明しながら、注目に値する個々の作品の社会的文化的意義と映画表現の新しさを、フォアマン、カサヴェテスやダルデンヌ兄弟など世界で知られる東欧の監督や欧米の重要な作家と比較しながら論ずる野心的なものであった。

