新しい監督?
毎年春にニューヨーク近代美術館(MOMA)とリンカーン・センターで共催される「新しい監督・新しい映画特集」(New Directors/New Films)は2013年で42回目を迎え、世界24カ国から19本の長編劇映画、6本の長編ドキュメンタリーと17本の短編が上映された。この“新しい”監督というのは、アメリカにとってという意味なので、アメリカ大陸はずっと太古の昔からあるのに、コロンブスが「発見した」というような滑稽な定義ではある。『家族ゲーム』(83)の森田芳光監督がこの特集からデビューしたというのはまだしも、今村昌平監督の『復讐するは我にあり』(79)や『楢山節考』(83)がこの特集で上映されているのは笑ってしまう。しかし、この特集からヴィム・ヴェンダース、テオ・アンゲロプロス、ピーター・グリーナウェイ、ミヒャエル・ハネケ、チェン・カイコー、ウォン・カーウァイ、ペドロ・アルモドバル、ジャ・ジャンクー、キム・ギドクなど世界の名だたる映画作家がアメリカに紹介され、アメリカ人監督でもジョン・セイルズ、チャールズ・バーネット、スパイク・リーなど現代のアメリカ映画を支えるそうそうたる面々がこの特集からデビューしている。今までの上映作品リストは壮観である。
『カメレオンの色』
2013年の特集の上映作品の中で“35年ぶりのブルガリア映画”と紹介された『カメレオンの色 (Tsvetat na hameleona/The Color of the Chameleon)』 (12、エミール・クリストフ監督)を、私は逃すわけにいかなかった。ブルガリアの共産党独裁政治に対する痛烈な風刺喜劇で娯楽色満点、日本でも是非上映して欲しい。独裁時代が終わろうとしていた1989年春、徴兵逃れがばれて脅され秘密警察で働かざるを得なくなった大学生バトコが主人公である。しかし映画の冒頭、彼を養っていた独身の叔母が、少年バトコを連れて警察を訪ねるシーンから、この映画はセックスに関する艶笑喜劇的様相を帯びているのが判る。この叔母も一筋縄ではいかない猛女で、彼女の秘密が解かれないままあの世に旅立つ。
(12、エミール・クリストフ監督)を、私は逃すわけにいかなかった。ブルガリアの共産党独裁政治に対する痛烈な風刺喜劇で娯楽色満点、日本でも是非上映して欲しい。独裁時代が終わろうとしていた1989年春、徴兵逃れがばれて脅され秘密警察で働かざるを得なくなった大学生バトコが主人公である。しかし映画の冒頭、彼を養っていた独身の叔母が、少年バトコを連れて警察を訪ねるシーンから、この映画はセックスに関する艶笑喜劇的様相を帯びているのが判る。この叔母も一筋縄ではいかない猛女で、彼女の秘密が解かれないままあの世に旅立つ。
大学の芸術かぶれのインテリたちが集まる「新しい思想を考える会」の監視を命じられたバトコは、情熱を持って仕事に励む。彼等は『ジンコグラフ(Zincograph亜鉛版)』という怪しげな哲学書の読書会に励んでいるのだが、昼間印刷工場で働き、夜は独自のスパイ網を作り上げて国家の安寧を脅かす男がこの本の主人公である。『カメレオンの色』の原作は、2010年に出版されたヴラデイスラフ・トドロフの小説『ジンコグラフ』である。
印刷工場に調査に出かけたバトコは、そこで会った若い女性と恋に落ちる。映画館の切符売りをしている彼女の仕事場では、黒澤明監督の『羅生門』(50)のポスターも見える。彼女はバトコにハリウッド映画『カサブランカ』(42)で、ハンフリー・ボガード演ずるリックに助けを求めてくる二人のブルガリア人が登場するシーンを見せるが、こんな場面が『カサブランカ』にあったとは私は気がつかなかった。
彼女は出遭った者に意図せずに災いをもたらしてしまう運命にあると自分で信じている。映画が進行するにつれ次々と本当にそうなってしまうのに爆笑するとともに、そのアイロニカルな結末に哀れも感じる筋立てとなっている。
印刷工場の親父も相当の変人で、一挙一動にぎょっとさせられる。旧ソ連のブレジネフとホーネッカー(東独の党首だった)の熱烈なキスをポップに描いたロシアのアーティスト、デイミトリ・フルベル(Dimitri Vrubel)による絵(1990年にベルリンの壁に描かれたもの)がこの工場にあるのもシュールリアルで、この絵が登場したときには観客から笑いが起こった。
バトコの下宿先の家主の女性による思わぬ手違いから、彼は任務を解かれる。しかしそれなりに職務に忠実で自分の仕事に愛着さえ感じている彼は秘密警察にいいかげんな部署をでっちあげ、その部署の名前の略「SEX」局の局員としての身分証明書を偽造してインテリたちの監視を独自に続ける。まさに『ジンコグラフ』の物語を実践するのである。
バトコはインテリたちをお互いに監視させる一方、荒唐無稽な要求を各自につきつけ、彼等のなすことを詳細に記録する。独裁時代には人民は独自にものを考えることを禁じられていて、いかに滑稽なことを言われても羊のように従っていたメンタリティの構造が想像できる。それとともに、秘密警察が独裁社会で機能する一つの理由は、他人の監視が隠れた喜びとなるという人間の心理も明らかになっている。
独裁体制が崩れると、このインテリたちはいかがわしい政治家になり、独裁時代に暗躍していた旧勢力も相変わらず権力の座にとどまっている。バトコは手に入れていた資料を駆使して、このイカサマ師たちを撃ち落していく。映画の題名のカメレオンとは、ぬめぬめと生き残っていくバトコのことだけではないだろう。どんな体制でも周囲の思惑を伺い、皮膚の色を変えながら生存能力を駆使し、何食わぬ顔をしてじっと動かないと思っていたら目も留まらぬ速さで舌を出して獲物を獲るようなコスい人間はあちらこちらに溢れている。
カフカ的不条理劇でもありながら、『カメレオンの色』は奇想天外な出来事に満ちていて楽しい。空虚な権威や人間の弱さをちくちくと批判しながら、余裕をもった速度で展開する独得な魅力である。ああ、と私は嘆息した。幼稚なコメディが溢れる日本でも、こんな大人の風刺喜劇映画が作られないものだろうか。
過去に紹介されたブルガリア映画
「新人映画特集」で紹介された35年前のブルガリア映画というのは、エドュアルド・ザカリエフ監督の『男の時代(Manly Times)』(78)である。インターネットで情報を調べてみると、以下のような時代物らしい。金持ちの男が近くの村で見初めた女性を二人の男に花嫁としてさらわせるが、その道中に女性はそのうちの一人と恋に落ちる。婚礼のテーブルの末席に座る彼女の恋する彼からの指図を待つ彼女の姿で映画は終わるらしい。私が前回のコラムで紹介したバルカンの隣国ルーマニアの映画『石の婚礼』(72)を思わせる。
「新人映画特集」の過去の作品リストを見ると『炎のマリア(Koziat Rog)』(72、メトー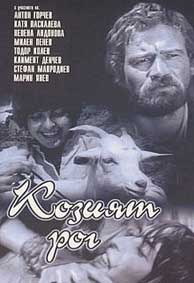 デイ・アンドーノフ監督)も1973年に上映されている。日本でも本作品は76年に岩波ホールで上映されているが、私は74年、『山羊の角』(原題の日本語訳でもある)というタイトルで京橋のフィルムセンターで上映された「現代ブルガリア映画の展望」シリーズの中で見ている。オスマン・トルコの圧政下のブルガリアの山村で、妻をレイプして殺した4人のトルコ人の男たちへの復讐を誓った男が、幼い娘を男として育て武術を叩き込む。成長した娘は山羊の角を武器にして探し出した男たちを父と殺し始める。しかし羊飼いの青年と恋におち、自分に課せられた行動の不毛さに、それを続けることへの疑問を感じ始める。実行の妨げになると父は山羊の角で青年を殺し、絶望した娘はその後を追う。山羊の角という武器に象徴されるブルガリア人は、他民族による支配下では正当な裁判も望めず、武器を持つことを禁じられていて空手の技術を身につけるほかなかった沖縄の民族の置かれた立場を連想させる。この映画の白黒の画面は、強烈な情熱と悲劇をみなぎらせていた。
デイ・アンドーノフ監督)も1973年に上映されている。日本でも本作品は76年に岩波ホールで上映されているが、私は74年、『山羊の角』(原題の日本語訳でもある)というタイトルで京橋のフィルムセンターで上映された「現代ブルガリア映画の展望」シリーズの中で見ている。オスマン・トルコの圧政下のブルガリアの山村で、妻をレイプして殺した4人のトルコ人の男たちへの復讐を誓った男が、幼い娘を男として育て武術を叩き込む。成長した娘は山羊の角を武器にして探し出した男たちを父と殺し始める。しかし羊飼いの青年と恋におち、自分に課せられた行動の不毛さに、それを続けることへの疑問を感じ始める。実行の妨げになると父は山羊の角で青年を殺し、絶望した娘はその後を追う。山羊の角という武器に象徴されるブルガリア人は、他民族による支配下では正当な裁判も望めず、武器を持つことを禁じられていて空手の技術を身につけるほかなかった沖縄の民族の置かれた立場を連想させる。この映画の白黒の画面は、強烈な情熱と悲劇をみなぎらせていた。
このフィルムセンターのシリーズで私は何本かのブルガリア映画を初めて観て、この未知の国への興味に渇望感を深めた。現代社会を描く作品もそれなりにおもしろかったが、トルコ支配下の時代を描く歴史物はどれもパワフルであった。今そのカタログを取り出してみていたら、2枚の黄色く変色しかかった紙が挟まれていた。
1983年10月6日から20日までMOMAでは、近年収集したブルガリア映画特集として、1958年から79年にかけて製作された11本を上映した。その中で私は『桃 泥棒(Kradetsat na praskovi)』(64、ヴーロ・ラデフ監督、フィルムセンターの特集でも上映されていた)と『根のない木(Durvo bez koreni)』(75、フリスト・フリストフ監督)を見ている。前者は第一次世界大戦中、捕虜収容所にいたセルビア兵と恋に落ちる大佐夫人の悲恋を、後者は農村から都会に出た男の直面する問題を描いた現代社会劇である。
泥棒(Kradetsat na praskovi)』(64、ヴーロ・ラデフ監督、フィルムセンターの特集でも上映されていた)と『根のない木(Durvo bez koreni)』(75、フリスト・フリストフ監督)を見ている。前者は第一次世界大戦中、捕虜収容所にいたセルビア兵と恋に落ちる大佐夫人の悲恋を、後者は農村から都会に出た男の直面する問題を描いた現代社会劇である。
MOMAで私は、2007年にも2本のブルガリア関係の映画を観ている。ブルガリア初の女性監督ビンカ・ゼリァズコヴァ(1923年生)の生涯を描くドキュメンタリー『ビンカ─沈黙についての物語を語る(Binka: To Tell A Story About Silence)』(06、エルカ・ニコロヴァ監督)が、ゼリャズコヴァ監督の代表作『私たちは若かった(A Byahme mladi/We were young)』(61)とともに上映された時だ(その解説は、こちら)。ニコロヴァはブルガリア出身で、ニューヨークのニュースクール大学で映画製作を学んだ。『ビンカ』は、この先駆的女性監督の作品からの映像や彼女を知る監督や評論家のインタビューを通じて、ゼリャズコヴァの功績を再発見しようとするものだ。妥協をすることがなかったゼリャズコヴァの作品はしばしば検閲で問題となり、上映禁止になっていたそうだ。
『私たちは若かった』は第二次世界大戦中、ナチスドイツの占領に対するレジスタンスに参加した若い男女のグループを描く、東欧映画によくある“レジスタンスもの”である。レジスタンス運動で出遭った男女が恋に落ちるが、男は組織からスパイと疑われる。男女ともナチスに逮捕され、少女は獄中自殺、青年は殺される。しかしこの作品の前衛的表現に私は驚いた。ヒロインの心情が、森の木のそばに立つ彼女や鳥が飛び立つイメージで、ストーリーに直接関係ない場面で詩的に挿入される。またレジスタンス仲間のアマチュア写真家で車椅子の少女が坂道から急転落して死亡する場面は、彼女を見下ろす人々をネガフィルムのようなイメージで捕える。社会主義リアリズムが強要された共産党独裁社会では、このような前衛的表現が検閲で問題になったと想像できる。また『私たちは若かった』は今から見れば歴史的に重要な映画に思えるが、フィルムセンターの「現代ブルガリア映画の展望」に入っていなかったのは、本作品が当時の政府映画機関の覚えが悪かったからだろうか。
最近のブルガリア映画
日本ではなじみのなかったブルガリアが急速に近くなってきたのは、なぜか立て続けに2本のブルガリア映画が最近劇場公開されたからだ。東京国際映画祭でグラ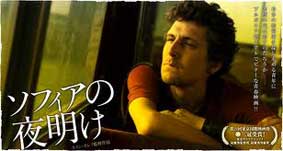 ンプリ、監督賞、主演男優賞(フリスト・フリストフ、前述の監督とは別人で、撮影終了直前に不慮の事故で死亡したのも話題であった)の三冠を得た『ソフィアの夜明け(英語題名Eastern Play)』(09、カメン・カレフ監督、公式サイトはこちら)は、2011年にシアター・イメージフォ-ラム等で公開された。続いてEU映画祭で上映されたブルガリア映画『世界は広い─救いは何処にでもある(英語題名 The World is Bigand Salvation Lurks Around the Corner)』(08、ステファン・コマンダレフ監督、公式サイトはこちら)は、2012年に『さあ帰ろう、ペダルをこいで』と改題され劇場公開された。
ンプリ、監督賞、主演男優賞(フリスト・フリストフ、前述の監督とは別人で、撮影終了直前に不慮の事故で死亡したのも話題であった)の三冠を得た『ソフィアの夜明け(英語題名Eastern Play)』(09、カメン・カレフ監督、公式サイトはこちら)は、2011年にシアター・イメージフォ-ラム等で公開された。続いてEU映画祭で上映されたブルガリア映画『世界は広い─救いは何処にでもある(英語題名 The World is Bigand Salvation Lurks Around the Corner)』(08、ステファン・コマンダレフ監督、公式サイトはこちら)は、2012年に『さあ帰ろう、ペダルをこいで』と改題され劇場公開された。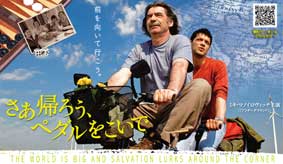
前者は現代のブルガリアの首都ソフィアで薬物やアルコール中毒と戦う38歳の主人公のイツォが、無為な生活の中で美しいトルコの女性と出会って希望を感じ始めるという作品だ。イツォの十代の弟は国粋的なスキンヘッドのグループに入り、旅行中のトルコ人一家を襲う。その一家を助けたことで、イツォは彼女と出会う。社会主義から資本主義に移行して20年経った社会で、行き場のない思いをうつうつとさせている若者たちの雰囲気が独得であった。
後者では、家族とドイツに移住していた主人公の青年アレックスが、一家でブルガリアに里帰りの途中交通事故に遭い両親と記憶を失う。アレックスは祖父と一緒に二人乗り自転車で旅をし、祖父の得意なバックギャモン(ボードゲーム)をすることで、祖父と心を通わせていく。独裁時代にブルガリアを去り、イタリアの収容所で苦労した話などをする祖父を演ずるのはセルビア人俳優ミキ・マノイロヴィッチだ。マノイロヴィッチはエミール・クストリッツァ監督の『パパは出張中!』(85)や『アンダーグラウンド』(95)でおなじみで、眉毛の濃い顔を見れば「ああ、あの人」とすぐわかる旧ユーゴ時代から人気のあった名優で、フランス映画などにも出て国際的活躍をしている。雑多で強靭なバルカン精神の真髄を具現しているようなマイノロヴィッチは出身のセルビアの隣国ブルガリアの人間としても十分に通用するということだろうか。

