アルバニアのイメージ
アルバニアというバルカンの小国は独裁制の下で長らく国が閉ざされていたため、日本でもアメリカでもなじみのない国である。私は2006年夏にマケドニアのアルバニアとの国境近くにあるオフリッド湖より車でアルバニアに入り、首都ティラナに2泊した。ベルリンの壁崩壊の影響がこの国にも及び、一党独裁から複数政党制度になったのが1990年でその後資本主義経済を取り入れ来た。私が訪れたティラナには社会主義時代のくすんで威嚇的な雰囲気の建物がまだ残っていたが、街の感じはあまり西側と変わらず、若い人たちは英語を喋っていた。
それまでにアルバニアといえば、私はトロント映画祭で独裁時代の地方の小学校教師の苦難を描く『スローガン』(01)を見て、アルバニア映画に興味を抱いていた。アルバニア訪問後、DVDで独裁政権崩壊後のアルバニア社会の現状を描く『ティラナ零年』(02、この映画はアメリカの映画祭で上映された)と、独裁時代と現在のアルバニアをつなぐ『月のない夜』(04)を見ていた。
私がアルバニアを訪れた2006年に日米で公開されたハリウッド映画スパイク・リー監督の『インサイド・マン(Inside Man)』(クライブ・オーウエイン、デ ンゼル・ワシントン、ジョディ・フォスター出演のハリウッド作品の傑作、英文公式サイトはこちら)で、アルバニアが登場する。マンハッタンの銀行に強盗一味が押し入り、人質をとる。警察側が仕掛けた差し入れのピザの箱に取り付けられた盗聴器から流れる言葉を、警察署の誰も理解できない。そこで銀行の周りに集まっている野次馬にその音声を流し、誰かこの外国語を理解できるものはいるかどうか尋ねると、清掃局員が名乗り出てそれはアルバニア語だというのである。その局員自身はアルバニア語を話せないが、アルバニア系の元妻がいつも親戚と喋っていた言葉だと言う。警察がアルバニア大使館とアルバニア国連代表部に通訳の協力を頼むと断られ、その清掃局員に頼み込んで元妻に来てもらう。
ンゼル・ワシントン、ジョディ・フォスター出演のハリウッド作品の傑作、英文公式サイトはこちら)で、アルバニアが登場する。マンハッタンの銀行に強盗一味が押し入り、人質をとる。警察側が仕掛けた差し入れのピザの箱に取り付けられた盗聴器から流れる言葉を、警察署の誰も理解できない。そこで銀行の周りに集まっている野次馬にその音声を流し、誰かこの外国語を理解できるものはいるかどうか尋ねると、清掃局員が名乗り出てそれはアルバニア語だというのである。その局員自身はアルバニア語を話せないが、アルバニア系の元妻がいつも親戚と喋っていた言葉だと言う。警察がアルバニア大使館とアルバニア国連代表部に通訳の協力を頼むと断られ、その清掃局員に頼み込んで元妻に来てもらう。
そのアルバニア系女性は自分の操るアルバニア語という特殊言語が、この場ではいかに貴重なものであるかよくわかっている。駐車違反の呼び出し状を山のように持ってきていて、これをまず警察に反故にさせる。それからおもむろに盗聴器から流れる音声を聞いて笑い出してしまう。20年も前に死んだアルバニアの独裁者エンヴェル・ホジャ(1908〜1985)の演説だというのである。完全犯罪を遂行する犯人は常に警察の一歩先を行き、盗聴器が差し入れの食品に取り付けられることを見越して、わざわざ誰もわかりそうもない言語のテープを仕掛けたのである。ここでのアルバニアはまさに、ほとんど誰も知らない遠い国であり、見当もつかない文化であった。
西欧を脅かすイメージとしてのアルバニア
次に私がアルバニアと出遭ったのは、フランスのリュック・ベッソンが製作・共同脚本でリアム・ニーソン主演の『96時間(Taken)』(08、日米公開は09 )であった。ニーソンは元諜報機関員を演ずる。離婚した妻との間の18歳の娘が友人とパリに行ってアルバニア系人身売買組織に誘拐されたのを、彼が単身取り戻しに行くスリラーである。このアルバニア系ギャング組織はナイーブな若い女性を拉致して、情け容赦なく国際的裏社会の面々に競り落とさせる。ひところはコロンビアの麻薬組織やロシア・マフィアとその手下のモンテネグロ・マフィアなどが娯楽映画では、西欧の平穏な生活を脅かす非人間的な国際的な犯罪集団とされていたと思うが、いつのまにかアルバニアが成り代わって、あるいは既存の国際的ギャング組織と競存するようになった。
)であった。ニーソンは元諜報機関員を演ずる。離婚した妻との間の18歳の娘が友人とパリに行ってアルバニア系人身売買組織に誘拐されたのを、彼が単身取り戻しに行くスリラーである。このアルバニア系ギャング組織はナイーブな若い女性を拉致して、情け容赦なく国際的裏社会の面々に競り落とさせる。ひところはコロンビアの麻薬組織やロシア・マフィアとその手下のモンテネグロ・マフィアなどが娯楽映画では、西欧の平穏な生活を脅かす非人間的な国際的な犯罪集団とされていたと思うが、いつのまにかアルバニアが成り代わって、あるいは既存の国際的ギャング組織と競存するようになった。
同じ時期にアート系映画に登場したアルバニアは、ベルギーの巨匠・ジャン=ピエールとリュック・ダンデルヌ兄弟の監督による『ロルナの祈り(Lorna’s 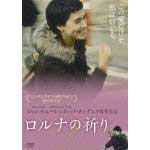 Silence)』(08、日本公開09)である。ベルギーでバーを開く夢を抱くアルバニア移民の女性ロルナが主演だ。ベルギー人の麻薬患者と結婚して彼を麻薬で死んだと装って殺し、彼女はベルギーのパスポートを手にする企みである。その後彼女がロシア移民のマフィアと結婚して彼にEUのパスポートを売りつけるという計画に手を貸してしまう。しかし彼女が麻薬患者に愛情を感じてしまったことから、この完全犯罪にひずみが入り始める。ここで描かれるアルバニアは経済的後進国で、何とか経済的先進国である西欧での成功をめざす人々が西欧に乗り込んできていることを背景としている。ここでも後進国のアルバニアが、西欧のまっとうな人々の生活を脅かしている。しかしさすがにダンデルヌ兄弟の作品なので、ロルナの人間としての悩みを通してその背景にある国際的経済格差から来る不平等や不正にまで観るものは思いを馳せることになる。
Silence)』(08、日本公開09)である。ベルギーでバーを開く夢を抱くアルバニア移民の女性ロルナが主演だ。ベルギー人の麻薬患者と結婚して彼を麻薬で死んだと装って殺し、彼女はベルギーのパスポートを手にする企みである。その後彼女がロシア移民のマフィアと結婚して彼にEUのパスポートを売りつけるという計画に手を貸してしまう。しかし彼女が麻薬患者に愛情を感じてしまったことから、この完全犯罪にひずみが入り始める。ここで描かれるアルバニアは経済的後進国で、何とか経済的先進国である西欧での成功をめざす人々が西欧に乗り込んできていることを背景としている。ここでも後進国のアルバニアが、西欧のまっとうな人々の生活を脅かしている。しかしさすがにダンデルヌ兄弟の作品なので、ロルナの人間としての悩みを通してその背景にある国際的経済格差から来る不平等や不正にまで観るものは思いを馳せることになる。
EU参加をめざして
NY近代美術館(MOMA)で毎年1月に上映されるグローバル・レンズ(Global Lens)という第三世界の国々を中心として紹介する映画特集を私は毎年楽 しみにしている。今年はアルバニア映画『恩赦(Amnesty/Amnistia)』(11、映画情報はこちら)が含まれていた。監督のブヤル・アリマニは1969年アルバニア生まれで、ティラナの芸術大学で絵画と舞台演出を学んだ後、1992年にギリシャに移住して映画助監督となる。短編映画製作を経て、この作品が長編第一作である。
しみにしている。今年はアルバニア映画『恩赦(Amnesty/Amnistia)』(11、映画情報はこちら)が含まれていた。監督のブヤル・アリマニは1969年アルバニア生まれで、ティラナの芸術大学で絵画と舞台演出を学んだ後、1992年にギリシャに移住して映画助監督となる。短編映画製作を経て、この作品が長編第一作である。
『恩赦』はEU参加をめざすアルバニアが、EUから要請された国内の政治経済制度改革の一つで、監獄の囚人の人道的扱いの着手を要請されたことから起こるドラマを描く。一ヶ月に一度、囚人の配偶者は刑務所を一時間訪れベッドを共にすることを許されることになる。詐欺と債務不履行で三年の刑を受けている夫を訪ねるエルサと、ヴィザ書類不備などで二年半の刑を受けている妻を訪れるスペテイムが毎月同じ日に刑務所に通い、出遭い、恋に陥る。
小学生の二人の息子、折り合いの悪い舅と同居するエルサは工場からリストラされ、食堂の賄いをして働いているが、日常生活は単調な繰り返しであった。印刷所に勤めるスペテイムはエルサより年配で落ち着いた心優しい男性である。この二人の俳優(ルリ・ビトリとカラフィル・シェナ)も地味だが素晴らしい。「仕事はどう?」と聞かれたエルサの「じゃがいも、玉葱、キャベツの繰り返し……」という答えが、心が躍ることもない彼女の生活を物語っている。刑務所の配偶者訪問の部屋も、質素なベッドが狭い部屋いっぱいに広がり、水道の水がぼたぽたと落ちている暗くてぱっとしない空間で、この映画の二人の男女が喜びを得られる場所ではない、当局がしつらえたおざなりの装置である。
この二人が心を寄せ合い身体を求め合うことから二人の生活に活気が出てくるが、当然エルサの舅の容認できることではない。エルサは刑務所で会った女友達の家に子供たちを連れて移り住み、新たな賄いの仕事も得る。しかし子供たちを無理矢理連れ去ろうとする舅ともめて突き倒す。そのうちに軽犯罪の囚人の恩赦が発表され、各々の配偶者が釈放されることでエルサとスペテイムの関係の終焉となる。
エルサを忘れられないスペテイムがエルサを訪ねた時、舅が猟銃でこの二人を銃殺する。そこへタオルを腰に巻いた裸のエルサの夫が出てきてうろうろしているところをカメラが遠景で捕らえるところで映画は終わる。
EU参加を前にして
EU参加というアルバニアの近代化の問題が、社会にまだ残る後進性と衝突する様相がこの映画では興味深かった。EU参加のために後進国がEUの国際基準に合わせる努力を強いられるテーマは、昨年のトライベッカ映画祭で少数民族教育改革に取り組むルーマニアの様相を描いたドキュメンタリー『私達の学校』(モナ・ニコアラ、ミルナ・コカ=コズマ共同監督)にもあった。その対象になるのはロマの子供たちで、ルーマニア人の学校に併合させる努力の過程が描かれる。ロマの子供たちについて理解のあるルーマニア人教師もない教師もいて、ロマの家族でも子供の教育に意欲的な親もいれば、早く娘を結婚させたがる親もいる。その道のりは楽ではない。
私が行った『恩赦』の上映は金曜日夜7時からで、金曜日の夕方はMOMAの入場が無料になるため多くの人々がMOMAを訪れるが、その影響もあるのか450人ぐらいの大講堂は満員であった。しかしアルバニア系と見受ける観客も多数いて、さながら「アルバニア・ナイト」という趣きであった。映画上映前のアリマニ監督の舞台挨拶によれば、この夜はアルバニアの元国会議員夫妻も観客の中に居たという。上映後後にアリマニ監督の質疑応答があったが、この映画のストーリーは監督が読んだ新聞記事の実際に起こった事件を基にしたものだそうだ。またこのような恩赦が実際に行われているのかという質問に対し、二年に一度クリスマスの頃に軽犯罪の囚人の恩赦が行われているとの答えだった。「この映画の中の二人に離婚という選択はないのか?」という観客からの質問に「アルバニア文化にはトルコの影響があり、西欧の離婚のように単純にはいかない」と監督は答えた。「エルサが刑務所で会う女性のアパートに一緒に行った時、二人の女性の間に性的にひかれるものはあるのか(私もその場面でそう思った)」という問いには「全くない」という答えである。「エルサの父親はムスリムのようだが、アルバニアのムスリムの文化について聞きたい」という観客の質問に、私の近くに座っていたアルバニア人と思われる中年男性が立ちあがり声を大きくして「アルバニアにムスリム系アルバニア人とかキリスト教系アルバニア人なるものは存在しない。いるのはアルバニア人だけだ」と言い放ち、周囲の人々が拍手した。
復讐のテーマ
図らずも2本のアルバニア映画を、続けて見ることになった。通常の人が興味を持たない地域の映画を見たい観客である私にとって、ニューヨークのこのような映 画環境はありがたい。2本目の映画『血の許し(The Forgiveness of Blood)』(11、アメリカ公開2012年2月末、映画の情報はこちら)は、新進のアメリカ人監督ジョシュア・マーストンがアルバニアの映画監督アンダミオン・ムラタイと共同で脚本(ベルリン映画祭脚本賞受賞)を書きアルバニアで現地俳優を使って撮影した作品である。マーストンは2004年、コロンビアから麻薬運びの仕事を引き受けるテイーンエジャーの女性を描く『マリア・フル・オブ・グレース』で注目され、次回作が待たれていた作家だ。その彼がアルバニアを舞台にした映画を選んだのは興味深い。
画環境はありがたい。2本目の映画『血の許し(The Forgiveness of Blood)』(11、アメリカ公開2012年2月末、映画の情報はこちら)は、新進のアメリカ人監督ジョシュア・マーストンがアルバニアの映画監督アンダミオン・ムラタイと共同で脚本(ベルリン映画祭脚本賞受賞)を書きアルバニアで現地俳優を使って撮影した作品である。マーストンは2004年、コロンビアから麻薬運びの仕事を引き受けるテイーンエジャーの女性を描く『マリア・フル・オブ・グレース』で注目され、次回作が待たれていた作家だ。その彼がアルバニアを舞台にした映画を選んだのは興味深い。
ニクとルデイナの高校生の兄妹の父はパンを近所に配達して生計を立てている。以前からもめていた隣人とある日争って、父と叔父が隣人を殺してしまい、叔父のみが警察に逮捕され父は逃亡した。この地方の掟で、この場合は加害者家族の男が被害者家族の復讐の標的になるため、加害者家族の男は家から出られなくなる。これで一生を終える例もあるそうだ。女しか外に出ることを許されないので、母と幼い妹弟を抱えルデイナが学業を止めて父の代わりにパン売りに出かけ、ニクは家の中で朝から晩までテレビを見たりして一日をぶらぶら過ごす。
ニクは同じ高校の女子学生と愛し合っていたが、この二人は携帯電話で写真を送りあったり話したりすることしかできなくなる。この二人を演ずるのは新人のトリスタン・ハリライとシンデイ・ラチェイで、撮影時まだ高校生だったが、二人ともカリスマ性があり新鮮な魅力がある。携帯電話やビデオゲームを楽しむ若者たちがこの何世紀にも渡り守り続けられてきた伝統に縛り付けられているというアルバニアの状況が何とも奇異だ。
これからが人生という若者が不条理な因習に縛られる悲劇であるが、この因習にもいろいろな側面が共存している。例えば何日かに一回はニクの弟の小学校の先生が家庭教師に訪れる。また被害者と加害者側家族の間の「調停役」が村の長老のような人たちを中心に形成されるが、その界隈で有名な調停役を雇うには高い料金がかかる。加害者側は被害者側に交渉して、何時間か男が外に出る権利を得たりする。
そして現代の若者であるニクは最後には被害者側家族に直談判にでかけるのである。何世紀にも渡る因習に意義を申し立てる若者の言い分は全面的には通らないものの、後進性の桎梏に甘んじていない新しい世代の抵抗が見られることは興味深い。
この果てしもなく続くニ家族の復讐というテーマは、『セントラル・ステーション』(98)や『モーターサイクル・ダイアリーズ』(03)で有名なブラジルのウオルター・サレス監督も映画化している。アルバニアのこの伝統を描くアルバニア出身、パリ在住のイスマイル・カダレの小説をブラジルの寒村に置き換えて映画化した『ビハインド・ザ・サン』(01、アメリカ公開01、日本公開04)である。ブラジルの寒村でも、このストーリーが観ていて違和感なく受け入れられたのは、この復讐の伝統がいかに普遍的に「前近代的」題材かということである。


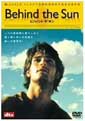
[セントラル・ステーション] [モーターサイクル・ダイアリーズ] [ビハインド・ザ・サン]
観客との質疑応答
『血の許し』のアメリカ劇場公開の前に、フィルム・ソサエテイー・オブ・リンカーン・センターの機関誌『フィルム・コメント』が選ぶ映画特集で2月中旬にこの映画が上映された。こちらの250席ほどの会場も満員で、熱気が感じられた。上映後の質疑応答では、舞台にマーストン監督、製作者のアメリカ人ポール・メゼー、主演の兄弟を演じたトリスタン・ハレライとシンデイ・ラチェイ、母親役のイリレ・ヴィンカ・チェライが登場した。
アルバニアに何世紀も続く復讐の掟の伝統は、独裁の社会主義国時代には行われていなくて、社会主義が倒れると同時に1990年代以降、再現したそうだ。このテーマを現代の若者の視点から描きたかったとマーストン監督。アルバニア人の日常生活に強い影響を与えているこの掟をめぐり、若者がどう対処していくのかを描きたかったというメゼー。若い世代の二人の俳優は、実際に自分の身辺に起こっている習慣ではないので、映画出演が決まってからリサーチをしたそうだ。
観客から、この復讐の掟は文字で書かれたものか口頭伝承のものかという質問があり、監督は自分がこの掟に興味があると言うと、必ず「掟を読んだか?」という質問をアルバニア人からされたが、実は文章化されていないと言う。それなのに、実に多岐に渡る細かい解釈がされているのが実情だそうだ。もう一つ、「歴史を尊重するか?」という質問をいつも同時にアルバニア人からされたそうだ。アルバニア人一般の歴史観から来るものだろうか。
若者の視点というだけでなく、男が社会的に役に立たなくなった時に実力を発揮しなければいけない妹や母親という女性の視点から描かれているという観客の感想に、監督は興味深いエピソードをあげた。映画の最後でニクが掟に立ち上がり、被害者家族の家長からこの地に二度と戻って来ないなら家から出て良いと言われる。アメリカ人はこの結末に、ニクは因習に立ち上がり、それから逃れることができたが、妹のルデイナは因習に捕らわれたままで可哀想だという感想を述べる。ところがアルバニアでは、故郷を離れなければならなくなったニクが可哀想だと皆が皆言うそうである。
ニクの父親がなぜ監獄へ行かないのかという観客の質問に、監督はアルバニアでは賄賂と腐敗が噂される警察への不信が強い実態があるからだと答えた。またこの映画はアルバニア北部の村が舞台だが、アルバニア人俳優たちは方言に気を使ったかという観客からの質問に、アルバニア系住民が多く最近セルビアから独立したコソボ出身のチエライ、映画の舞台となったシュコドラ出身のハリライとラチェイのほか、マケドニア内のアルバニア系住民の多い都市テトヴォ出身の俳優もいて、出身地は異なるが皆が和気あいあいと家族のような雰囲気で撮影が進行したとチェライが流暢な英語で語った。バルカンの複雑な民族地図を見た一瞬であった。>
アカデミー賞外国語映画部門の対決
MOMAの上映で『恩赦』のアリマニ監督は、実はアルバニアにはあまりよい脚本家がいないと断言したり、小さな国の狭い映画の世界でこんなことを言ってもよいのかと思っていたら、実はもっと熾烈な対立があったのだ。映画の上映前に近代美術館の担当者が、「この映画はアルバニアからのアカデミー外国語映画賞エントリー作品です」とこまごまと外国語映画賞の説明をした。私はアルバニアでは多分年間数本以下しか製作されていないだろうから、400本以上製作されている日本などの国とは事情が違うなあと思っていたら、アリマニ監督が昨年アルバニアで製作された二本の中から選ばれたと続けた。
後にリサーチしてみると、エンターテイメント専門誌『ヴァラエティ』がアルバニアのアカデミー外国語賞エントリーをめぐる対立について書いていた。その記事によれば、昨年アルバニアで製作されたのは四本で、当初はエントリーを決定する委員会が『血の許し』を選んでロサンゼルスのアカデミーに提出した。そうしたらこのアリマニ監督が『血の許し』は監督がアメリカ人、脚本がアメリカ人とアルバニア人の共同、撮影のロブ・ハーデイと編集のマルコム・ジェミソンがイギリス人、製作はアメリカ、アルバニア、イタリア、デンマークの共同で、アルバニアの代表にするには外国人のアーテイストの参加が顕著すぎて失格であると抗議した。アカデミーは再検討して、『血の贖い』を失格として、再検討をアルバニアの委員会に要請。委員会は今度は『恩赦』を選んだそうだ。
この決定について、批判的な第三者のアルバニアの監督の言葉が載っていた。アカデミーの規約を検分した上でアルバニアの委員会が選出した作品を失格としてやり直しを命じたアカデミーへの不満である。当然落選したマーストン監督は、「これはアルバニアの物語りでアルバニアの俳優、アルバニアの多くのスタッフが作ったアルバニア映画だ。これをアルバニア映画と認めないで、どうしてフランス人の俳優がフランス語を喋るフランスで撮影されたアキ・カウリスマキ監督の『ル・アーヴル』がフィンランド代表で、バルカンを舞台にしてクロアチア語が大半をしめる『As If I Am Not There』がアイルランド代表なのか?」(監督、共同脚本、製作、撮影、編集がアイルランド人らしい)と逆襲している。
そもそも外国語映画賞は過去にも何度も問題になっている。『恩赦』もアルバニア、ギリシャ、フランスの合作であるが、国際的合作が増えてから、映画の国籍の問題は常に出てくる。上記のように監督の国籍と使われている俳優の言語が一致しなかったり、さまざまな国から参加するアーテイストの問題がある。2006年にはオーストリアのミヒャエル・ハネケ監督がフランス人俳優、主にフランス語で撮った『隠された記憶(Cache)』(05)という素晴らしい作品が、フランスもオーストリアも代表として出品できなかったという結果になってしまった。
2008年にはイスラエルから出品された『迷子の警察音楽隊』(07,英語題名は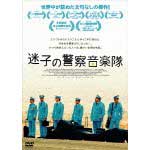 Band’s Visit、日米公開07年)が、その台詞の中で英語が話されている時間が映画上映時間の50%以上を占めるという抗議がロサンゼルスのアカデミーに届いた。再審査の結果、アカデミーはこの映画を失格とし、イスラエルの委員会は『ボーモント』という映画を再提出した。その後で、『迷子の警察音楽隊』の製作者たちが、アメリカのアカデミーに告げ口したのは『ボーモント』の製作者と監督だと騒ぎ出した。そもそもエジプトの楽隊がイスラエルに言って話が通じないというストーリーなので、共通言語としてかなりひどい英語でお互いに喋るという設定で、製作者によれば84分に映画のうち、22分が英語、18分がアラビア語かヘブライ語だそうだ(この事件を報道した『ニューヨーク・タイムス』誌による)。この話を聞くと、「50%以上出品国の言語であること」という規約がいかに馬鹿馬鹿しいか痛感できる。『ボーモント』の製作者側は、いや我々はイスラエルの委員会に意見を述べたが、アメリカのアカデミーとは連絡を取っていない。むしろ話題づくりで『迷子の警察音楽隊』のアメリカの配給会社のソニー・ピクチャーズ・クラシックの策略だろうと逆襲。ソニー側は「そんなことはしていない。でも1つの国から多くの素晴らしい作品が製作されるとこのような対立はよく起こる」とコメントをして、もう泥仕合である。
Band’s Visit、日米公開07年)が、その台詞の中で英語が話されている時間が映画上映時間の50%以上を占めるという抗議がロサンゼルスのアカデミーに届いた。再審査の結果、アカデミーはこの映画を失格とし、イスラエルの委員会は『ボーモント』という映画を再提出した。その後で、『迷子の警察音楽隊』の製作者たちが、アメリカのアカデミーに告げ口したのは『ボーモント』の製作者と監督だと騒ぎ出した。そもそもエジプトの楽隊がイスラエルに言って話が通じないというストーリーなので、共通言語としてかなりひどい英語でお互いに喋るという設定で、製作者によれば84分に映画のうち、22分が英語、18分がアラビア語かヘブライ語だそうだ(この事件を報道した『ニューヨーク・タイムス』誌による)。この話を聞くと、「50%以上出品国の言語であること」という規約がいかに馬鹿馬鹿しいか痛感できる。『ボーモント』の製作者側は、いや我々はイスラエルの委員会に意見を述べたが、アメリカのアカデミーとは連絡を取っていない。むしろ話題づくりで『迷子の警察音楽隊』のアメリカの配給会社のソニー・ピクチャーズ・クラシックの策略だろうと逆襲。ソニー側は「そんなことはしていない。でも1つの国から多くの素晴らしい作品が製作されるとこのような対立はよく起こる」とコメントをして、もう泥仕合である。
この結果、「出品国の言語が50%」という規約が改正されたのではないだろうか 。というのは昨年のカナダの出品作でノミネート作品となった『灼熱の魂(Incindies)』(10、ドウニ・ヴェルヌーヴ監督、日米公開は11)は、舞台はある中東の国で台詞もアラビア語が大半を占めていたように思うし、『ル・アーヴル』になれば全編フランス語であり、フィンランド語ではない。
。というのは昨年のカナダの出品作でノミネート作品となった『灼熱の魂(Incindies)』(10、ドウニ・ヴェルヌーヴ監督、日米公開は11)は、舞台はある中東の国で台詞もアラビア語が大半を占めていたように思うし、『ル・アーヴル』になれば全編フランス語であり、フィンランド語ではない。
『血の許し』マーストン監督は、実は処女作『マリア・フル・オブ・グレイス』も一端コロンビアから出品された後、主要アーテイストがコロンビア人ではないということで、失格になった過去がある。
元来小さな国になればなるほど、人間関係がそれなりにあって、狭い世界の中での内輪もめがあるという話はよく聞く。アカデミー外国映画賞選出をめぐるアルバニアやイスラエルのドラマを次は見たい。
追記
第三回コラムの校閲をしていただいたバルカン研究の柴宜弘氏が、第二回コラムに登場するルーマニア映画『モルゲン』を、その後ルーマニアから帰国した友人から手に入れたDVDで見て、以下の指摘をされた。『モルゲン』の中でクルド人をかくまう主人公が、村人たちに「こいつはロマだ」と紹介しているシーンがある。それで村人たちも不法移民とは思わず、騒ぎ立てなかったのではないか。またそこには、ロマに対する社会的背景もあるのではないか、という点である。柴氏に感謝し、これを記す。

