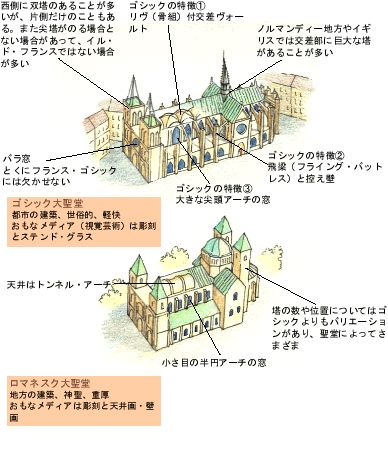パリの北隣 にもかかわらず、ぶらぶら猫はこの夏(2002年8月)までこの街に足を踏み入れたことがなかった。いやバスや電車で何度も通ることはあった。なにしろサン・ドニはパリからシャルル・ド・ゴール空港へ向かうルート沿いにあり、その車窓から見える1998年に開かれたワールドカップ・フランス大会の決勝会場となったスタッド・ド・フランスはサン・ドニ市にある。しかし、サン・ドニ市内の駅で降りて、市内を散歩したことはなかったのだ。 それはなぜか? 今回訪問した大聖堂以外に、とりたててめぼしい観光名所がないためでもある。最近はスタッド・ド・フランス目当ての観光客もいるようだが、グランド・アルシュ(新凱旋門)のあるデファンス地区(クールブヴォワ、ピュトー市)やヴェルサイユ宮殿(ヴェルサイユ市)のようなスーパースターがサン・ドニにはいない。
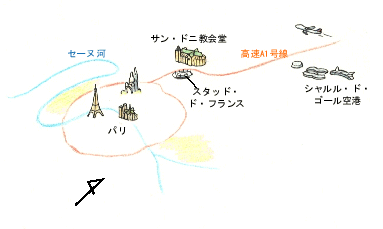
サン・ドニの場所 危険な街? ぶらぶら猫がサン・ドニを訪れなかったのは、そのあまりに悪い「評判」のためである。とにかく危険なごろつきがのさばる無法地帯で、近づくべからずという噂を誰かから聞いたか、勝手に思い込んだか、映画『ニキータ』に描かれた不良者が闊歩するニューヨークのハーレムのような場所と恐れおののいていたのである。であるからゴシック発祥の地といわれ、歴代フランス王家が菩提寺としてきた教会がこの街にあるとわかった時、なんでそんな所にあるのだと嘆きたい気持ちになったものだ。 さて、サン・ドニ大聖堂であるが、その起源は3世紀にさかのぼる。宗教にはつきものの奇妙きてれつな伝説によると、サン・ドニという名前の由来となった最初のパリ司教である聖(サン)ドニSaint-Denisは、250年にパリのモンマルトルの丘で斬首されたが、その直後に自分の首を持ったまま北へ向かって歩き出し、冒頭で紹介したように6000歩行ったのち、現在のサン・ドニの地で死んだのだという。 いざサン・ドニへ サン・ドニ駅前は、超モダンな建物が立ち並び、未来都市のような様相を呈している。ハイパー・マーケットのカルフールをはじめ、商店が並んでにぎやかだが、パリらしい伝統的建物はあまり見られないし、中世の由緒ある教会を訪れるにふさわしい場所とは思えない。まあ、日本の伝統的街並みを残す代表的都市?である京都を訪れる外国人が京都駅を見た時の驚きにくらべれば、たいしたことではない。 あいにく雨が振り出す中、個性あふれる近代的建物群を小走りに抜けると、目ざす教会堂が姿をあらわした。さすがに由緒ある教会だけあって、周囲の建物よりも一頭抜きんでた高さがあるが、圧倒されるほどの迫力ではない。身廊天井までの高さ29mは、パリのノートル・ダム大聖堂などより一回り小さいし、鐘楼も南側に1本しかなく調和を欠いている。
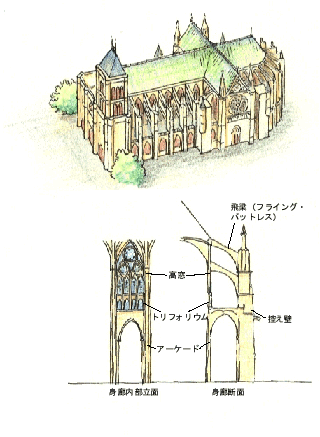
サン・ドニ大聖堂俯瞰(ふかん)図と身廊立面図(左下)、身廊断面図(右下) サン・ドニ大聖堂の見所 サン・ドニ教会堂の見所がその内陣やクリプトの墓にあることは、入場料が必要なことからもわかる。フランスのたいていの大聖堂は内陣周歩廊を歩くだけならお金はいらない。クリプトに入るためや塔に登るためにお金を払わなければならない大聖堂は多いが、地上部分は外陣 、内陣ともに入場自由なのが普通である。ところがサン・ドニ大聖堂は外陣と袖廊(トランセプト)の間に柵があり、内陣に入るためには一度外に出て、大聖堂南側にあるゲートで入場料を払い、袖廊南扉口から入りなおさなければならないのだ。 内陣の様相は他の大聖堂と大きく異なる。そこかしこに歴代国王や王妃の墓碑が並んでいるのだ。棺のような直方体の石の上に浮き彫り彫刻のついただけのものから、天蓋付の立派なものまで形はさまざまである。ルイ○○世、シャルル○○世とフランス史をいろどる国王たちの墓が並んでいるが、素人にもなじみのあるのはフランス革命で犠牲になったルイ16世とマリ・アントワネットの墓である。1793年にパリのコンコルド広場でギロチン刑にかけられた直後はマドレーヌ墓地に葬られていたらしいが、王政復古時代にサン・ドニに移されたのだという。 ゴシックとシュジェール ロマネスクの修道院も、史上最大のロマネスク教会堂をたてたクリュニー修道院をはじめとして、聖職者のイメージからかけ離れた、相当に世俗的欲望にまみれた世界であったらしいが、ゴシックの誕生にも、シュジェールのような俗っぽい人物が必要だったということだ。 サン・ドニ大聖堂を出発点としてイル・ド・フランスの地に競うようにたてられることになるゴシック大聖堂の数々も、純粋に神を敬う気高い志によってというよりは(もちろんそれもあったではあろうけれども)、「おらが街にも隣街より立派な大聖堂を」という見栄や競争心が原動力となったのだ。
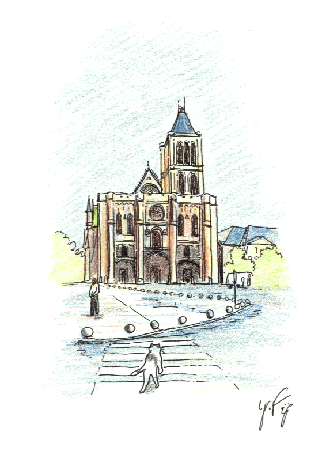
サン・ドニ大聖堂前広場からのスケッチ サン・ドニの街 サン・ドニの歴史は5世紀に、パリの守護聖女ジュヌヴィエーヴがサン・ドニの墓の上に教会をたてたことにはじまる。以後、サン・ドニは修道院を中心とした門前町として発展し、カロリング朝ルネサンス期には写本挿絵や金銀細工が盛んになるなど、文化都市の性格が強かった。それが19世紀の産業革命期になり、パリに近い立地が認められ、セーヌ河に通じるサン・ドニ運河の開通もあって、工場や労働者が次々と移り住んで産業都市へと一変した。化学・薬品工業から金属・電器工場まで、第2次産業の街としてサン・ドニ市は戦後フランスの高度成長を支えるが、1970年代以後、長引く経済の停滞と公害問題などにより、工場は地方に移転していった。 現在のサン・ドニ市は工場跡地を文化施設や緑地などに変える再開発に取り組み、再び産業都市から文化都市へと脱皮しようとしている。サン・ドニ市が、フランス王家ゆかりの、そして最初のゴシック芸術たる大聖堂にふさわしい都市に生まれ変わるのも、そう遠いことではないかもしれない。
|